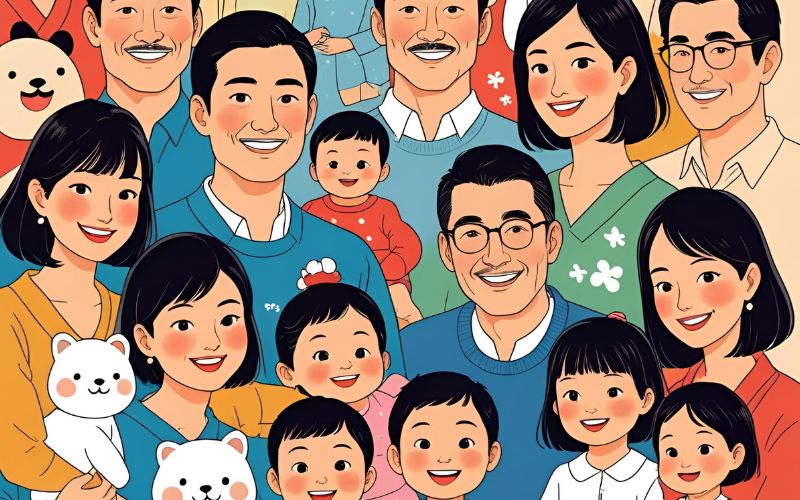戦後、日本はまず「経済を急速に成長させる」ことを国家目標としました。その中で「家庭は専業主婦が守る」というモデルは、夫の所得を最大化するための「家庭内支援体制」でした。
▼関連記事▼
【家族と年金①】昔の主婦に年金がなかったってホント?
【家族と年金②】「専業主婦の黄金時代」ってどんな時代?
【家族と年金③】子育て多様性認める社会へ ~国益で変化する年金制度、専業主婦、共働き〜
戦後から経済発展の旗振りとしての「専業主婦」
1950〜70年代の高度経済成長期には、女性は家にいて子育て・家計を担い、夫が会社で働き続けるという社会モデルが理想とされました 。この方が個性より組織を重視する日本の発展にとっても都合がよかったのです。
1980年代の「黄金の専業主婦制度」
1985年、労働市場と年金制度は大きな転機を迎えました。夫が会社で払う年金に乗って、専業主婦も年金を手に入れられる仕組み(第3号被保険者制度)が整ったのです。
この時期、バブル景気で夫の収入が高く、専業主婦は安心して家庭にいられる“黄金時代”が完成しました。世界的に見ても珍しい「終身雇用制」「専業主婦制度」が高度経済成長を後押ししました。
バブル崩壊後の「生活の変化」と女性の社会進出
しかし1990年代のバブル崩壊による長期的不況時代に入り、夫だけの収入では暮らせない家庭が増えました。それと同時に女性も仕事に出るようになり、政府も「女性活躍推進」を国家戦略に据えました 。
企業の制度改革や育休制度の拡充、女性の社会参画支援が急がれるようになり、専業主婦制度は徐々に後退していきます。
年金制度は国家経済に連動する
年金制度は常に“国益=経済成長”とリンクしています。
戦後は経済発展に合わせて専業主婦を支える方向へ。けれども今は、人手不足と少子高齢化に対応するため、女性の労働参加が国策として推し進められています 。
年金制度を維持するためにも、女性の労働力増加が必要になっているのです。つまり、高齢者を含め「国家総動員」的に日本を支えていく局面に入ってきました。
2025年の年金制度改正では、週20時間以上の労働で企業規模に関係なく社会保険加入が段階的に義務化されるなど、女性の社会進出を後押しする改革が進みます。
経済成長と人口維持の2大目標のために
ただし「女性に働いてもらえれば出生率が上がる」わけではありません。社会が望むのは“仕事も家庭も両立できる環境”です。
東京都では、2025年4月から「週4日勤務」「保育所の送迎のための労働時間短縮」など、働く親を応援する施策が進んでいます 。
政府は、経済成長と人口維持という二つの国家目標に向けて、
- 女性の働きやすい制度整備(保育・育休・柔軟な働き方)
- 第3子以降の支援拡充(子ども手当月3万円など)
- 更に「子ども誰でも通園制度」では専業主婦の子育ても支援
これらを同時に進めようとしています。
今後の課題と予想される動き
| 課題 | 対策・予想 |
| 働くか家庭に入るかのジレンマ | 夫婦で選択できる制度整備(柔軟な勤務×育休) |
| 年金・税制から見た不公平感 | 共働きと専業主婦を問わず、公平に支える制度へ改革 |
| 少子化・人口減少 | 保育・教育費負担軽減+地域支援+移民活用の議論も |
| 価値観の多様化 | 共働き・専業・パートなどを「選択肢」として尊重 |
社会保障と育児支援は今、「共働きプラス育児支援」が国家戦略となっています。
従来の「専業主婦=幸せ」モデルは崩れつつあり、夫婦それぞれが“自分たちに合ったあり方”を選びやすい制度へと変わろうとしています。
さらに日本の伝統的な「専業主婦」も選択肢に入ってくるのです。
🌟まとめ
- 戦後の「専業主婦優遇」は経済発展のための国家戦略だった
- 1980年代に年金制度が最も専業主婦に優しかった
- 今は働く女性を後押ししつつ、出生数を上げるための支援も進む
- 将来的には、日本経済の発展とリンクしつつ、「働き方」「家庭の在り方」の多様性を受け止める社会が理想
(執筆者:スモール・サン)