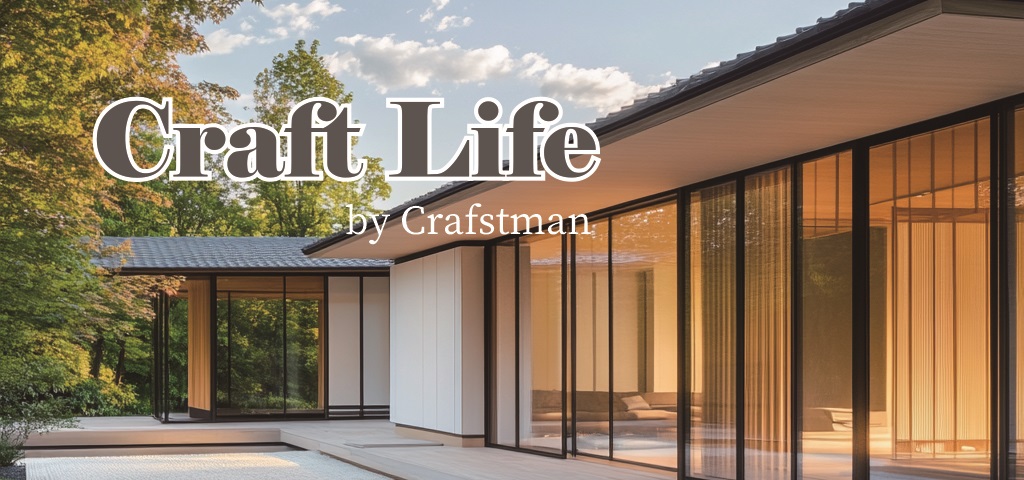「建築物」のコストはどのように算出するのでしょうか。
建物の基本部分は、「建築面積」「延べ床面積」で概算を出すことができます。
コストに差がでる部分は、土地条件の違い(古家の存在や地盤補強の有無)、求められる耐震性や耐久性・断熱性能の違い、立地特性(商業地か住宅地か)によります。個別には、間取り・収納・外構などの条件によって変わってきます。
AからPの16の項目の見積もりを積算します
本サイトでは、AからPの16の項目(最後のPは諸経費および手続き費です)
に分けて、見積もりの明細を算出します。
それぞれの項目は工事単位にしても手続きにしても、それなりに大きなものです。
私は「資材の調達」と「原価計算」の仕事をしておりますので、こまかいようですが、
見積もり計算の考え方を解説しておきます。
住宅の見積もりは、各項目で共通することですが、
➀原材料・部材費用
②工賃(工事全般・造作にかかる人件費)・機械の使用料
③管理コスト(現場監督費用、住宅メーカーの営業コスト・事務経費・上乗せ利益など)
に分けられます。
重要なことなので繰り返しますが、
●「原材料・部材費用」「工賃・機械の使用料」「管理コスト」です。
時系列で言いますと、「仮設工事」から始まって、最後の「外構工事」まで、
「製造原価」というものは、すべてこの尺度で「原価計算」をします。
どの住宅メーカーでも、積算を担当する部隊がこのような算出を行っています。
たとえば「Bの基礎工事」だと、「コンクリートの使用量(立方メートル、立米(りゅうべい)とも言います)」「砕石の量」「配筋・コンクリート打設の職人の手配とその日数」「油圧ショベル・圧送ポンプ車のレンタル料」「鉄筋の本数」「型枠の数」「防湿シートの枚数(平方メートル)」などです。
「Cの大工工事」だと、「土台・柱・梁・桁・胴差」などの構造材の数、「根太・垂木・間柱・筋交い」などの羽柄材の数、「構造材の枚数」「プレカット費」「材木の運搬費」「大工の手間賃(工事期間の日数分)」「上棟時の建て方手伝い手間」「釘・ビス・テープ」「建て方のクレーン費」などです。
見積もりの変動要素は、「立地や建物の個別条件」「施主の要望(好み)」によって発生します
本サイトでは、「標準的な仕様」によって見積もりを作成しています。
変動要素については、
●「立地や建物の個別条件」によって発生するもの
●「施主の要望(好み)」によって発生するもの
があります。
「立地や建物の個別条件によって発生する項目」は、オプションで追加できるようにしています。
また、施主の希望や好みによって「発生する項目」についても、オプションで追加できるようにしています。
施主が「同じ要望を出しても」住宅メーカーの営業マンによって受け取り方が違い、また「見積もりが異なる」こともあります。
1.原材料・部材費用 2.工賃・機械の使用料 3.管理コスト について説明します。
1「原材料・部材費用」は「材料メーカー」からの仕入れ価格・市況価格により変動します。
「材料単価」というと「固定的なもの」と思われる方もいるかもしれませんが、実は「単価」にはいくつかの種類があるので説明します。
まず、
●カタログ単価(略称 R:Retail Price)、です。これは文字通り、メーカーでカタログに掲載したり、対外的に表示したりする単価です。
次に
●市況単価(略称 M:Market Price) です。これは市場で取引されている金額です。いろんな調査があるのですが、業界団体が定期的に調査しているもの、調査会社が調べたもの、新聞に載っているものなど、さまざまです。代表的なところでは、経済調査会の「積算資料」、建設物価調査会の「物価資料」があります。
最後に、
●「住宅メーカー」の実際の仕入れ単価(略称 B:Buying Price) です。
この3番目の「仕入れ単価」は、メーカーの仕入力によってかなり差が出ます。
もっとも差がつくところではないかと思います。その会社に勤める営業マンでも「実際に会社がいくらで仕入れているのか」は知らないと思います。
もちろん、営業マンでも「住宅の原価」については、ある程度知っているかと思いますが、会社から「この部材はこの金額で計上してください」と決まった数字を提供されているだけで、真実は「会社の奥のほう」に存在するはずです。
一般的に高い方から、
●カタログ単価 > 市況単価 > 仕入れ価格
が成り立つと思います。
あと、原材料には「材料費のみ」で計算する場合と、「施工費(工賃)」を含めて計算される場合が
あります。後者を「材工共」と書いて「ざいこうとも」単価と呼びます。
次に、2の「工賃」ですが、
主に施工業者(職人さん・大工さん)の人件費になります。
こちらも市況や経済状況により変動します。工事に技術を要するかどうかのレベル、地域によって単価は異なります。
また単価の基本的な考え方は、1人1日いくら?です。1日は8時間で計算しますが、4時間で終わる仕事なら0.5。2人で3.5日かかる仕事なら、7×単価で計算します。
3「管理コスト」は、
建設の現場でかかる「管理コスト」と、住宅メーカー側の「管理コスト(広告宣伝費や事務所経費ですね)」と分けて考える場合があります。後者は、損益計算書では「販売費および一般管理費」と呼ばれる部分です。
住宅メーカーは、材料メーカーとの仕入れ条件によりコスト削減ができます。「原材料コスト」や「宅地造成費」には地域差があります。2の工賃については、工事工程や人割りの見直しにより削減できます。住宅メーカーは、1と2コストを減らすほど「利益の上乗せ」ができます。これを「メーカーの企業努力」と呼びます。
住宅メーカーの営業マンは、「1と2のコストを所与のものとして」、一定以上の利益を上乗せすることを求められます。営業マンは、その会社の「標準パッケージ」で建設ができる場合に、最も安い見積もりを出すことができます。
見積もりが高くなる原因は、
「発注者にかかるコミュニケーションコスト(個別要求や仕様の変更など)」
「間取り・造作物に関する個別要因(特別仕様など)」
「土地にかかる個別要因(土壌調査、家屋撤去、造成・地盤改良など)」があります。
なお、建築費の概算として「坪単価」が使われることがありますが、
これは施主への説明用に、単に「建築費の総額」を延べ床面積の坪数で割ったものです。
住宅メーカーが、建物の原価を「坪単価」で算出することは絶対にありません。
しかも、建築費の中に「外構費用」が入っていなかったり、「電気工事代」が含まれていなかったりして、注意が必要で、施主にとても分かりにくかったりします。
このパートの最後に、「見解の相違」についての考え方を申し上げておきます。
「見解の相違」とは、専門家の間にもある意見の食い違いのことで、ときおり施主を迷わせてしまうことがあります。
「耐震等級は2が良いか3が良いか」「床下断熱は入れるべきかどうか?」とか、いろいろありますが、結論から言うと、「自分が立てる土地条件を勘案して、自分で決めてください」です。
たとえば、「南海トラフ地震が懸念されている地域で住宅会社を経営されている専門家の方は、耐震等級は3のほうが望ましい」と言います。これは、ある意味「当たり前」ですよね。地震があまり発生しない、地盤のしっかりした土地に家を建てようとする方だったら、また違った判断になるかと思います。
こういった、「住宅性能面」での基準の話は、特に意見が分かれがちです。あくまで「自分の土地条件、自分の優先順位、価値観」に基づいて、決めていただければと思います。