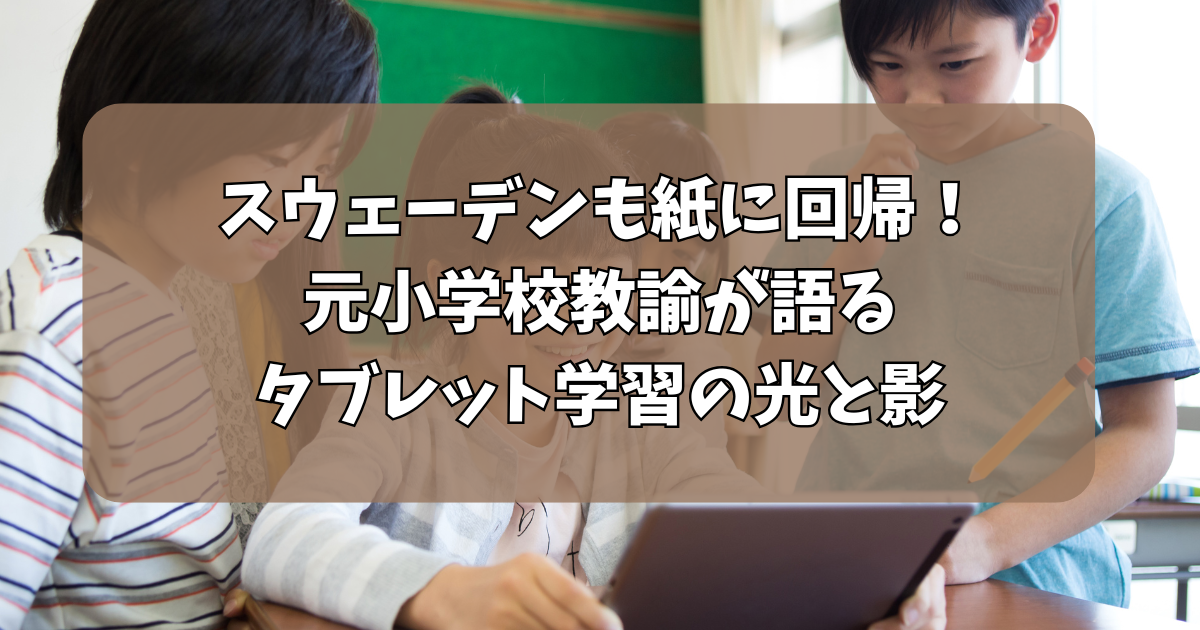タブレットやパソコンなどのICT機器が、学校現場に急速に広がったこの数年。
GIGAスクール構想のもと、1人1台端末の整備が進み、子どもたちは日常的にデジタル教材やアプリを活用するようになりました。
デジタル教材を使った学習は、確かに便利で効率的な側面もあります。
しかし現場で教壇に立っていた私の実感としては、「学びの質は本当に高まったのだろうか?」という疑問もぬぐいきれません。
実際、タブレットの長時間使用による集中力の低下や依存、学習へ取り組み方の変化に戸惑う子どもたちの姿をたくさん見てきました。
この記事では、元小学校教諭として感じたタブレット学習の“光と影”をお伝えしつつ、今、北欧など海外で起きている「紙への回帰」の動きにも触れながら、これからの教育のあり方を考えてみたいと思います。
近年急速に進んだ学校現場へのタブレット導入
日本の小学校では近年、タブレット端末の導入が極めて急速に進み、現在では原則すべての児童に1人1台の端末が配布されている状況です。文部科学省が主導する「GIGAスクール構想」のもと、全国の公立小中学校におけるICT環境の整備が推進され、2024年時点で普通教室の98%以上で端末の利用が可能となっています。
この流れが本格化したのは、2020年の新型コロナウイルス感染拡大を契機とした休校措置により、学校教育のデジタル対応が急務となったことが背景にあります。結果として、わずか数年で端末配布から運用までが一気に加速し、児童生徒1人あたりの端末保有台数は1.1台にまで到達。タブレットは教室の中だけでなく、自宅学習やオンライン授業といった場面にも活用の幅を広げています。
2024年度には、「週3回以上」タブレットを活用している学校が全体の約90%に達しており、活用頻度の高さは全国的に定着したと言えるでしょう。
具体的な活用例
筆者が勤務していた学校では、おもに下のような場面でタブレット端末を活用していました。
- 国語や算数でのデジタルドリルによる反復練習や進捗管理
- プレゼンテーション・パンフレット作成などの表現活動
- 欠席時のオンライン授業や、家庭学習の動画教材による補完
- クラス全体での共同編集や意見交換
- 週末や長期休暇の宿題
このように、タブレットは文部科学省が推進する「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立を目指す上で、極めて有効なツールとして期待されています。
一方で、現場ではいくつかの課題も浮き彫りになっています。
主な運用上の課題
- 教員のICTスキル格差と、デジタル教材の準備・活用にかかる負担
- 端末の故障・破損といった物理的トラブル、保険や管理ルールの整備不足
- 児童の使用時間のコントロール、端末の使い方指導、保護者との連携
- 更新時期に伴う財政的負担や廃棄処理の問題(いわゆる「2025年問題」)
- ネットトラブルや依存傾向、SNSを介したいじめへの対応
さらに、2025年度からは「GIGAスクール構想第2期」がスタートし、端末の更新・ネットワーク高速化・生成AI活用への対応といった教育DX(デジタル・トランスフォーメーション)が加速していく見込みです。
つまり、日本では先進国の中でも極めて高い普及率と利用頻度を実現している一方で、運用や教育効果の面では依然として模索が続いているのが現状です。
現場の教師はどう見た?タブレット学習の光と影

タブレット端末の導入によって、学習環境が確かに便利になったと感じる場面も多くありました。たとえば、授業中に早く課題を終えた子どもが、個別にタブレットで反復ドリルに取り組むことで、「やることがない時間」が減り、学習のテンポが途切れにくくなったのは大きなメリットです。
また、週末の宿題をアプリで配信・回収することで、教員側の集計・管理の負担が軽減されたり、意見をリアルタイムで集約できるツールを活用することで、授業中に子どもたち全員の声を拾いやすくなるといった利点も感じていました。
しかし、タブレットの活用が日常的になっていく中で、負の側面の方が強く意識されるようになっていったのも事実です。
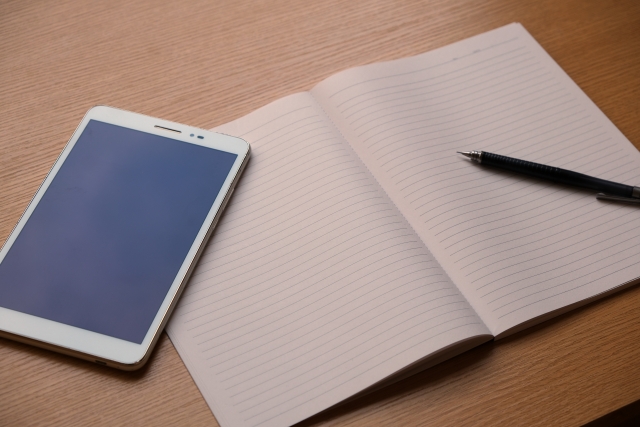
たとえば、あるアプリのチャット機能を使って、子どもたちが授業中にこっそりメッセージを送り合ったり、特定の子への悪口を書き込んだりするなど、目に見えにくいトラブルが起きるようになりました。さらに、休み時間にも「タブレットで遊びたい」と言い続けるなど、依存傾向が強くなってきた子どもも見られました。
また、不登校や欠席がちな児童ともタブレット越しにやり取りできるようになったこと自体は一つの進歩でしたが、その一方で、教員側の対応業務は確実に増え、心身の負担も大きくなったと感じます。
加えて、端末の扱い方やルールが学級や学年ごとにバラバラであったため、使い方をめぐるトラブルもたびたび発生していました。
印象的だったのは、成績上位の子どもたちはタブレットを上手に使いこなしていたのに対し、学習に苦手意識のある子はかえって気が散ってしまい、学びに集中できなくなるという傾向があったことです。これは私自身だけでなく、周囲の教員たちの間でも共通して語られていた実感です。
結局のところ、どんなに便利な道具があっても、教科書とノートを使ったアナログな学習こそが、すべての基礎になる。その力をしっかり育てた上で、デジタルの利便性を補助的に活用することこそが、本当に意味のあるタブレット活用なのではないか。そう強く感じるようになりました。
北欧や諸外国は規制の方向へ…タブレットが与える負の側面

タブレットをはじめとするデジタル端末の学習利用は、世界各国で一時期大きく広がりを見せました。
特にスウェーデンやデンマーク、オランダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは、2010年代から「一人一台」政策を進め、国語・算数・理科・社会といった教科で積極的に端末を活用する体制が整えられてきました。中でもスウェーデンは「授業中の端末使用時間が最も長い国」とも言われ、デジタル教育の先進例として注目されていました。
また、オランダの「スティーブ・ジョブズスクール」では、児童が1人1台のiPadを使ってアプリやクラウドを活用し、自らのペースで学習を進めるスタイルが確立され、教育の個別最適化の象徴的な取り組みとして話題になりました。
しかし近年、このようなデジタル重視の教育方針に見直しの動きが広がっています。
学力低下や心理的リスクへの懸念
フランス(2018年)、イタリア(2022年)、フィンランド(2023年)、そして2024年にはイギリス・スウェーデン・オランダ・オーストラリアといった国々が、小中学校でのスマートフォンやタブレットの使用を制限・禁止する政策を相次いで導入。こうした規制の背景には、「子どもの集中力や読解力の低下」「依存症リスク」「ソーシャルスキルの育成への悪影響」といった懸念が根強くあります。
実際にスウェーデンでは、デジタル端末の導入以降、PISAなどの学力調査で読解力の低下が見られたことがきっかけとなり、教育政策が大きく転換されました。紙の教科書を明示的に重視し、低学年でのデジタル使用を廃止する方針も打ち出されています。
さらに、ユネスコは2023年の報告書で「過度なICT利用は学力の低下と関連がある」と警告し、デジタル技術の教育効果には限界があることを世界に向けて発信しました。
「年齢・教科に応じた使い分け」への転換
一方で、アメリカやフィンランド、エストニアなどの国々は、タブレット活用を完全にやめるのではなく、明確なルールのもとで段階的に活用する方針を採っています。
例えば、低学年では紙教材を中心とし、高学年や特定教科のみ端末を使用するなど、児童の発達段階に応じた運用が主流です。また、ICTツールを使う際も、グループワークやプレゼンなど「目的が明確な場面」に限定する傾向があります。
ICT教育が特別支援や学力下位の児童に対して有効であるというポジティブな報告もありますが、各国ともに共通しているのは、「すべての子どもに一律で使わせるのではなく、目的と段階を見極めて慎重に導入すること」が重視されている点です。
世界が向かうのは「紙とデジタルのバランス」
こうした動向から見えてくるのは、かつてはデジタル学習の旗手であった北欧諸国でさえ、その限界と弊害に直面し、アナログな学びへの回帰を始めているという現実です。
今、先進国の多くが目指しているのは、
「紙とデジタルのバランス」
「エビデンスに基づいた段階的な導入」
という方針です。
単なる最新技術への飛びつきではなく、子どもの発達と学力形成を見据えた“慎重で柔軟な運用”こそが、これからの教育に求められている姿なのです。
まとめ|日本の教育現場とデジタル活用の今後
ここまで見てきたように、日本ではGIGAスクール構想のもと、小学校段階からタブレット端末の活用が急速に広まりました。個別最適な学びや協働的な学びを支えるツールとして一定の効果は見られる一方、依存傾向や集中力の低下、SNSトラブルといった負の側面も無視できない課題となっています。
実際、北欧をはじめとする多くの先進国では、こうした問題を受けて、「年齢に応じた段階的導入」や「デジタルと紙のバランス重視」へと方針を転換し始めています。教育現場におけるICT活用は、もはや「導入すること」が目的ではなく、「どう使い、どう制限するか」が問われるフェーズに入ったといえるでしょう。
私自身、教員としての経験から、タブレット端末の導入は小学4年生頃からが望ましいと感じています。もちろん低学年でも工夫次第で活用は可能ですが、機器の操作や自己管理がまだ未熟な時期に導入することで、かえって負の影響が大きくなる場面を多く見てきました。
だからこそ、今後のデジタル活用においては、
- 文科省が「どの場面で使うのか」という明確なガイドラインを整備すること
- 「導入したから使う」ではなく、目的に沿った必要最小限の利用にとどめること
- 子ども自身や保護者にもリスクを共有し、使用の意義と注意点を伝えていくこと
が、これまで以上に大切になってくると考えています。
教育の本質は、子どもたち一人ひとりの力を伸ばし、未来を切り拓くための「学び」をどう支えていくかということにあります。タブレット端末は、その一助にはなり得ても、決して万能ではありません。
紙と鉛筆でしっかりと「考える力」「書く力」「読む力」を育てたうえで、必要な場面で適切にデジタルを取り入れる。
そんな“バランスあるICT教育”こそが、これからの日本の教育に求められている姿ではないでしょうか。
暮らしのヒントがもっと見つかる「Craft Life」
部屋づくりのヒント、子どもとの暮らしをもっと楽しむアイデア、
そして、慌ただしい日々の中でも“ほっとひと息”つける時間の作り方——。
そんな“小さな工夫”が、毎日の家事や育児を驚くほどラクにしてくれます。
「Craft Life」では、子育て中のママ・パパに寄り添いながら、
家族みんなが心地よく暮らせるアイデアを日々発信しています。
たとえば…
- 片づけが自然と続く“しくみ”のつくり方
- 子どもの「やりたい!」を引き出す収納の工夫
- 家事をラクにする習慣の整え方 などなど。
読みやすく、すぐに実践できるヒントが満載です。
登録無料!暮らしの“ミニ知恵袋”が届きます
Craft Lifeのメルマガでは、忙しい毎日を助ける暮らしの工夫をギュッと凝縮してお届け。
すきま時間にサッと読めて、明日から役立つ情報ばかりです。
- 買ってよかった育児グッズ
- 忙しい日のための時短アイデア
- 赤ちゃんが生まれたらもらえるお金の話
登録はもちろん無料。
あなたの暮らしがもっとラクで、もっと楽しくなるヒントを受け取ってみませんか?
▼メルマガ登録はこちらから▼
(執筆者:AKKA)