子育て中の部屋って、どうしてこんなに一瞬で散らかるんでしょう。
朝片付けたはずなのに、夕方にはおもちゃも服も床いっぱい・・・なんて、あるあるですよね。
- 片付けようとした瞬間に子どもが泣きはじめる
- せっかく片付けても、1時間後には元通りでため息
- もう動けない…って日ほど、部屋だけは容赦なく荒れていく
こんな毎日が続くと、イライラが積み重なって自分の心まで散らかっていくような感覚になります。
「私ばっかり片付けてる」
「ちゃんとした親じゃないのかも…」
「なんでこんなにイライラするんだろう」
そんなふうに、自分を責めてしまう人も少なくありません。
でも、はっきり言います。
そのイライラは“あなたの弱さ”のせいではありません。
子育て期の部屋は“散らかって当たり前”という構造の問題なんです。
ここからは、
・心が軽くなる視点
・今日からできる現実的な工夫
・そして「もしかして家の広さとモノの量が合っていない“家のキャパ”問題かも?」と気づくポイント
を順にわかりやすくお伝えしていきます。
なぜ片付けてもすぐ散らかる?“あなたのせいじゃない”子育て期の部屋の仕組み

子育て期の部屋が片付かないのは、段取りや努力の問題ではありません。
理由はもっとシンプルで、もっと構造的です。
毎日「散らかるイベント」が多すぎるから
乳幼児〜未就学児がいる家庭では、
- おむつ替え
- 服の着脱
- おもちゃの遊び替え
- 絵本・工作の広がり
- 食事の準備と片付け
- 持ち帰りのプリント
こういったタスクがが常に発生し続けます。
つまり、散らかるスピードが片付けのスピードを確実に上回るんです。
どれだけ丁寧に片付けても、数時間後には「元通り」になっているのは、構造的に当然。
「片付けられる容量」より「家族人数×荷物量」が勝っているから
小さな子ども、とくに子供が2人以上いると、ちょっと必要なものを買い足しただけでモノの総量はどんどん増えていきます。
でも、住まいが賃貸の2LDKだったり、収納が少なかったりすると、
そもそも“仕舞う場所がない”ものが出はじめる。
これはもう、整理術の問題ではありません。
心が削られるのは「片付かない」からではなく、“片付けても戻る”から
多くの親御さんが言うのは、「散らかるからストレスなのではなく、片付けても片付けても終わらないのがつらい」という声。
これは心理学的に言うと、「努力が報われない状態」が続いているからなんです。
つまり、イライラするのは心理学的にもむしろ正常な反応です。
「自分の心が狭いから・・・」なんて、自分を責めなくて大丈夫です。
「全部きれい」は目指さない。イライラを減らす“心構え”と片付けの線引き
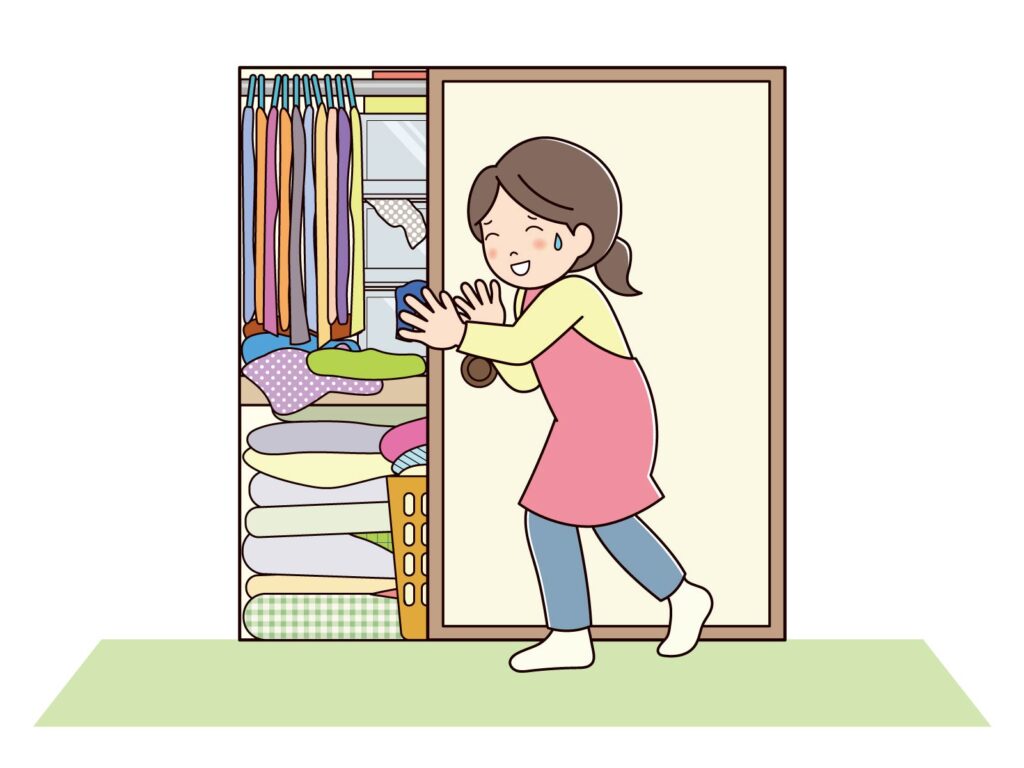
次に、片付けのストレスを劇的に減らすための“心構え”をお伝えします。
どれも難しいものではなく、「見方をちょっと変えるだけ」で心がふっと軽くなるはずです。
①子育て期の部屋は「散らかっていて正常」と知る
前述した通り、乳幼児が家の中で過ごす時間が多い時期は、部屋が散らかるのは当然。
乳幼児でなくても、お子さんが多ければ多いほど汚れるのは誰も止めることはできません。
“部屋の乱れ=親の管理不足”ではありません。
SNSの整った部屋は、別の条件の“別世界”。比べなくて大丈夫です。
②“モデルルーム”ではなく「回る家」を目指す
すべてを完璧に片付けようとすると、必ず心が折れます。
目指すのは“完璧”ではなく…
今日一日が回る“最低限の整い”でOK。
例えば、
- 通路だけは確保する
- ダイニングテーブルだけは夜にリセット
など、“死守するエリア”を決めれば十分です
③「私だけが片付ける」をやめ、家族のプロジェクトに変える
片付けは本来、家全体の仕事であり、誰か一人の担当ではないですよね。
子どもにも“小さなお片付け担当”をつくったり、夫が休みの日に家族で一緒にリセットする時間をつくるだけで、「どうして私だけ…」の気持ちは減っていきます。
どうしても「なんで私ばっかり!」が消えない時は、思い切って“片付けを手放す”という選択肢も検討してみて下さい。数日散らかり放題だったとしても、取り返しのつかない問題になる事はそうないはず。自分を癒す方が先決ですよ。
④収納術の前に、「家×モノの相性」を見る
どれだけ頑張っても片付かない場合、原因は「収納力の不足」ではなく、
“部屋のキャパよりモノが多い”状態
または
“そもそも間取りが子育て期に合っていない”状態
であることもあります。
ここに気づけると、“自分が悪い”から解放されていきます。
今日からできる5つの行動

最後に、今日から試せて、気持ちが軽くなる行動をお伝えします。
①まず「OKライン」を決める
完璧を目指すのではなく、“ここだけ整っていたら大丈夫”という場所を1〜2ヶ所決めます。
- テーブルだけは夜にリセット
- ソファの上だけは散らかさない
これだけで、心の負担は大きく減ります。
②散らかりを3種類に分けてみる
いきなり片付ける前に、まず“散らかりの正体”を見える化します。
- A:毎日必ず出るもの(おもちゃ・着替え)
- B:放置しても困らないもの(本・紙類)
- C:そもそも収納場所がないもの
Cが多い場合は、家がキャパオーバーのサイン。
③1日5分の“家族いっしょリセット”をつくる
朝か夜の5分だけでOK。大人も子どもも一緒に動くのがポイント。
「ママが片付ける」ではなく、“家族で部屋を整える時間”を作ってみましょう。
子どもが全然言うことを聞いてくれない日もありますよね。それでも、「片付けはみんなでするものだよ」と少しずつ伝えていくことで、すぐじゃなくても、少しずつ一緒に動ける場面が増えていきます。
④「収納を増やす」より先に、“持つ量の上限”を決める
散らかる原因の多くは、家の収納力より物の量が勝ってしまうこと。この状態では、収納グッズを増やしてもすぐ溢れます。
だから最初に、「ここに入る分だけ持つ」という“量の上限”を決めるのが効果的。
- 絵本はカゴ1つに収まるだけ
- おもちゃは棚1段に入る分まで
- 服はハンガーの本数で管理
ルールが明確だと、自然と散らかりにくくなりますし、子どもと一緒に「何を残すか」選ぶことで、持ち物を管理する力も育っていきます。
⑤今の家の「限界ポイント」をメモしておく
今の家が合わないと感じる部分を、そっとメモしておきます。
- 室内干しスペースが足りない
- リビングが狭く、片付けても戻りやすい
- 収納が圧倒的に足りない
これは“今の家でできる工夫”と“家自体の問題”を分ける作業でもあります。
まとめ
子育て中の部屋が散らかるのは、あなたがだらしないからでも、頑張りが足りないからでもありません。
むしろ、毎日必死にまわしている証拠。
心構えを整えて“今日できる最低限”を決め、家族で少しずつ回していく仕組みをつくるだけで、部屋の見え方も、気持ちの軽さも変わっていきます。
そして、いくら工夫してもどうしても限界を感じるなら、“住まいの問題”として切り分けてOKです。次の家を考える時の条件として、忘れずにメモしておきましょう。
あなたが少しでもラクに過ごせる家づくりのヒントが、今日の中に見つかっていますように。
(執筆:あい)



