(更新日:2025年11月27日)
2025年度から始まった高校・大学の学費無償化制度により、より多くの家庭が教育費の負担を軽減できるようになりましたね。
そんな疑問をお持ちの方に向けて、2025年から2026年に向けての最新の制度内容と申請方法等を分かりやすく解説します。
高校・大学の学費無償化とは?最新のポイントをわかりやすく解説

まずは学費無償化の制度全体像を、「学費無償化とは何か?」という基本的な疑問から、2025年から2026年での最新の変更ポイントまで詳しく、わかりやすくお伝えします!
■学費無償化の仕組みとは?〜授業料が実質ゼロになる制度〜
「学費無償化」と聞くと「学校に通うのがタダになる!?」と思いがちですが、実際は少し違います。
例えば、授業料そのものがゼロになるわけではなく、国や自治体が「授業料相当額を支援する」ことで、家庭の負担を大きく軽くする仕組みです。
高校の無償化の場合で言うと、高等学校等就学支援金制度(高校等の授業料支援制度)は、学校を通じて支給される「返済不要の支援金」です。
このように、無償化=“完全にゼロ負担”というわけではなく、「実質的に授業料負担がほぼなくなる」ケースが多いという点がポイントなんですね。
また、学費無償化には以下のような狙いがあります。
- 教育費の負担を軽くすることで、家庭の経済的な理由で「進学をあきらめる」という状況を減らす。
- 特に高校・大学という「次の学びのステップ」が経済的に壁にならないよう、機会平等を図る狙いがある。
- 教育を受ける機会を広げることで将来の人材育成という観点からも国や自治体が力を入えている分野である。
■【2025年・2026年】最新の制度改正ポイント
近年、この学費無償化制度には重要な変更がありました。特に「2025年度」、「2026年度」にかけて大きな動きが出ています。
主なポイントを以下のように整理します。
学費無償化でいちばん気になるのが「自分の家庭は対象になるのか?」という点ではないでしょうか?
以下では、高校と大学、それぞれの制度ごとに「誰が対象なのか」をわかりやすく整理していきます。
高校の学費無償化|対象者・支援額・条件・所得制限撤廃を解説!

高校の無償化とは、国が行う「高等学校等就学支援金制度」のことです。
この制度は、公立・私立問わず、日本国内の高校等に通う生徒の授業料を支援するものであり、その対象者は「いつから」「誰が」支援を受けられるかが大きく変わってきました。
ここでは、制度の基本対象者や条件をチェックするとともに、所得制限の最新の変遷についても解説します。
1. 対象となる学校種別〜高校・専修学校・高専など〜
高等学校等就学支援金制度の対象となるのは、日本国内に住所を有し、以下の学校などに在学する生徒です。
2.無償化の対象者は?所得制限撤廃で『国公立・私立』全世帯が対象に!
支援金の支給額を決める上での最も重要な要件が「所得」でした。しかし、近年の改正により、この所得制限は段階的に撤廃され、「すべての世帯」が対象となる方向へと転換しています。
【第一段階として、国公立高校の無償化がスタート(2025年度〜)】
2025年4月からは、国公立高校の授業料について、所得制限が実質的に撤廃されました。
| 変更前(〜2024年度) | 変更後(2025年度〜) | ||
| 支援対象者 | 年間所得910万円未満の世帯が対象 | ⇒ | 所得制限なしで全世帯が対象 |
これにより、年収910万円以上の世帯も含め、すべての世帯で国公立高校の年間授業料相当額(11万8,000円)が支援され、国公立高校の授業料は実質無償化となりました。
国公立高校の授業料について、11万8000円が全世帯支援対象に!
【第二段階として、私立高校の実質無償化へ(2026年度〜)】
2026年4月からは、さらに支援が拡充され、私立高校の授業料についても所得制限が撤廃される方針です。
| 現行の私立高校授業料支援 | 2026年度〜(予定) | ||
| 支援対象者 | 年間所得590万円未満世帯に最大39.6万円を補助 | ⇒ | 所得制限なしで全世帯が補助 |
| 支給上限額 | 39万6,000円 | ⇒ | 45万7,000円に引き上げ |
支給上限額の45万7,000円は、私立高校の全国平均授業料に相当する額です。
これにより、2026年度からは国公私立問わず、全国すべての世帯を対象に、授業料が無償化されることになります。
都道府県独自の支援について:東京都など一部の自治体では、国に先駆けて独自の支援制度を設け、すでに所得制限を撤廃し私立高校の授業料無償化を実施しているケースもあります。
3. 支援の対象は「授業料」のみ!自己負担費用に注意
就学支援金制度は、あくまで「授業料」を支援する制度です。以下の費用は支援の対象外であり、自己負担が必要となります。
| 自己負担が必要な費用 | 費用の目安 |
| 入学金 | 国公立:約5,000円、私立:約20万円程度 |
| 通学費 | 交通費、定期代など |
| 教材費・設備費 | 教科書、学用品、制服代、学校の設備費用など |
| 部活動費 | 部費や遠征費など |
授業料以外の費用については、低所得世帯を対象とした「高校生等奨学給付金」(返還不要)や、都道府県独自の経済的支援制度の利用を検討しましょう。
大学の学費無償化|多子世帯は所得制限なしに!【2025年度~】

高校の無償化と同様に、大学でも、経済的な理由で進学を諦めることがないよう、国による支援制度が設けられています。これが「高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)」です。
この制度は、「給付型奨学金」と「授業料・入学金の減免」を組み合わせて支援を行うもので、近年の改正により、特に多子世帯への支援が大きく拡充されています。
1. 大学無償化制度の対象者は?〜2020年から2025年の拡充経緯〜
大学無償化制度は2020年4月にスタートしました。当初は主に世帯年収約380万円未満の世帯の学生が対象でしたが、2024年度の拡充を経て、2025年度にはさらに支援対象が拡大されました。
| 当初(2020年度) | 拡充後(2024年度) | 最新(2025年度〜) | |
| 世帯年収の目安 | 約380万円未満 | 約600万円未満(多子世帯など) | 所得制限撤廃(多子世帯) |
| 主な対象者 | 住民税非課税世帯など | 多子世帯(子3人以上)、私立理工農系学生など | 多子世帯(子3人以上)の全世帯 |
| 支援内容 | 授業料減免+給付型奨学金 | 授業料減免+給付型奨学金 | 授業料減免(全世帯)+給付型奨学金(所得基準あり) |
2.多子世帯(子3人以上)無償化の条件
2025年度の改正で、多子世帯への支援は劇的に変化しました!以下に、支援の内容、無償化の条件を詳しく解説します。
A. 所得・世帯条件:所得制限の撤廃
最も大きな変更点は、多子世帯に対する所得制限が撤廃されたことです。
- 世帯所得:世帯年収に関係なく、大学等の授業料と入学金の減免支援を受けられます。
- 多子世帯の定義:3人以上の子どもを「同時に」扶養している世帯が対象です。
B. 支援の上限額(授業料・入学金減免)
多子世帯への支援は、主に授業料と入学金の減免として行われます。支援には上限が設けられており、進学先の学校種別によって異なります。
| 学校種 | 国公立/私立 | 授業料減免上限額(年額) | 入学金減免上限額(1回限り) |
| 大学(昼間制) | 国公立 | 53.58万円 | 28.20万円 |
| 私立 | 70.00万円 | 26.00万円 | |
| 短期大学(昼間制) | 国公立 | 39.00万円 | 16.92万円 |
| 私立 | 62.00万円 | 25.00万円 |
C. 学業要件
多子世帯の支援を受ける学生にも、以下の学業要件を満たすことが求められます。
- 学業意欲:
将来、社会で自立・活躍する目標を持って学習に取り組む意欲があること。 - 学修成果:
支援が継続されるには、出席率や修得単位数などが一定の基準を下回らないことが必要です。基準を下回った場合は「警告」が発せられ、改善が見られない場合は支援が打ち切られる可能性があります。
D.新制度の対象となる高等教育機関
新たな多子世帯向けの学費無償化制度の対象となるのは、以下の高等教育機関です。
- 国公立大学
- 私立大学
- 短期大学
- 高等専門学校(4・5年生)
- 専門学校
幅広い教育機関が対象となるため、多くの方がこの制度の恩恵を受ける可能性がでてきます。
3. 子ども2人以下の世帯の無償化条件【現行(2024年度)】
子ども2人以下の世帯については、2025年度の拡充の対象外であり、現行(2024年度)の所得制限が適用されます。
| 世帯年収目安 | 授業料等減免 | 給付型奨学金 |
| 約270万円未満(住民税非課税世帯) | 全額支援 | 全額支援 |
| 約300万円未満 | 3分の2支援 | 3分の2支援 |
| 約380万円未満 | 3分の1支援 | 3分の1支援 |
| 約600万円未満(私立理工農系のみ) | 4分の1支援等 | - |
その他の条件
- 資産要件: 学生本人と生計維持者の資産額の合計が、生計維持者2人の場合は2,000万円未満、1人の場合は1,250万円未満であること(不動産は除く)。
- 学力基準: 成績だけでなく、学修意欲があることが重視されます。面談やレポート提出などにより、将来の目標を持って学習に取り組む意欲が確認されます。
学費無償化の申請方法|手続きの流れ・必要書類・期限
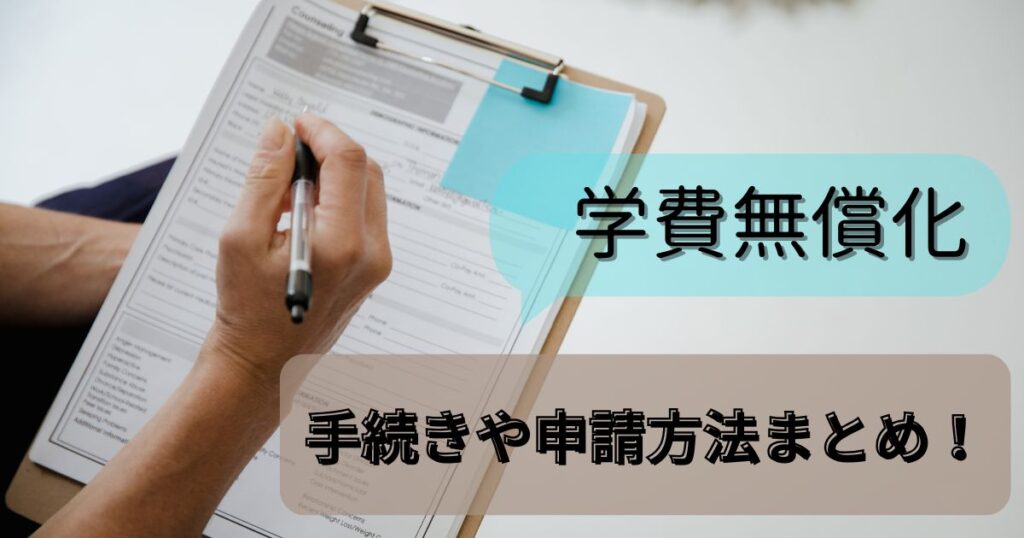
学費無償化の制度を利用するためには、いつ・どこで・何をすればいいのかを知っておくことが大切です。
ここでは、高校と大学それぞれの手続き方法を「最短で迷わずできる」ようにまとめました。
■ 高校の手続き方法(高等学校等就学支援金)
高校の無償化は、基本的に学校が取りまとめて申請します。
家庭の作業はそこまで多くありませんのでご安心くださいね。
【手続きの流れ】
- 入学時または年度初めに、学校から案内が配布される
- マイナンバーの提出(所得判定に必要)
- 必要書類(住民票・課税証明書など)があれば提出
- 学校が事務処理 → 国の審査
- 支援金が学校に交付され、授業料に自動的に充当される
【必要書類の例】
- 保護者のマイナンバー
- 課税(非課税)証明書
- 住民票
- 学校から配布される申請書
※ 所得が確認できる場合、追加書類が不要なこともあります。
※ 多子世帯は「兄弟姉妹の在学証明」を求められる場合があります。
■ 大学の手続き方法(高等教育の修学支援新制度)
大学の場合は学生本人が申請します。
高校よりステップが多いですが、大学側が案内してくれるので心配はいりません。
【手続きの流れ】
- 高校在学中に「予約申請」が可能(任意)
- 大学入学後、学生課・奨学金窓口で制度説明を受ける
- マイナンバー提出などで 世帯の所得判定
- 授業料減免の申請
- 給付型奨学金も希望する場合は同時に申し込む
- 審査後、授業料が減額され、奨学金は口座へ振り込み
【必要書類の例】
- マイナンバー
- 住民票
- 課税(非課税)証明書
- 大学が指定する書類(学業状況の提出など)
■ 手続きでよくある注意点まとめ
下記では、手続きや申請時に間違いやすい点や注意点をまとめました。申請する前にぜひ一度目を通してみてくださいね。
- 期限に遅れると、その年度の支援が受けられない
特に大学は「前期」と「後期」で期限が分かれているため注意が必要です。 - 世帯年収が変わった場合は再申請が必要
転職・退職などで状況が変わったら、学校に必ず相談してください。 - 書類不備による差し戻しが多い
マイナンバー・住民票・課税証明書の 年度・発行日 に注意。 - 自治体の追加支援を受ける場合、別申請が必要
都道府県が独自に補助しているケースでは、別途申請することがあります。
※参考URL:【所得制限ナシ】子ども“3人以上”で大学無償化へ…政府「第3子悩んでいる人に」 効果は?
授業料以外の費用を軽減!併用できる給付金・奨学金制度

ここまで、高校・大学の学費無償化制度についてご紹介してきました。
しかし、無償化されるのは主に「授業料」です。 実際には、教科書代や通学費、入学金など、 授業料以外にも多くの費用がかかります。
そこで活用したいのが、国や自治体が用意している 各種給付金・奨学金制度です。 これらを組み合わせることで、教育費の負担をさらに軽減できる可能性があります。
■まず確認したい!高校生等奨学給付金(国の制度)
国の制度として、最も多くの方が対象となる可能性があるのが「高校生等奨学給付金」です。
これは、主に低所得世帯の高校生に対して、授業料以外の教育に必要な費用(教科書代、学用品費、通学費、生徒会費、PTA会費など)の一部を給付する制度です。
【対象となる世帯の目安】
- 住民税非課税世帯
- 生活保護受給世帯
- その他、経済的に困窮している世帯
【給付額について】
都道府県や世帯の状況、学校の種類(全日制、定時制、通信制)によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 世帯区分 | 全日制・定時制(年額) | 通信制(年額) |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 約5万円 | 約5万円 |
| 非課税世帯(第1子) | 約14万円 | 約5万円 |
※金額は都道府県によって異なります。詳細はお住まいの都道府県教育委員会にご確認ください。
▶️全国の高校生等奨学給付金(専攻科含む)のお問合せ先一覧はこちら
この給付金は、授業料が無償化されたとしても、かかってしまう教育費を支援するものであり、経済的な負担が大きい家庭にとっては非常に重要な制度といえます。
返済不要の給付型なので、該当する方は必ず申請しましょう。
【申請方法】
申請方法や支給額、対象となる所得基準などは、お住まいの都道府県の教育委員会にお問い合わせください。一般的には、在学する高校を通じて申請書類が配布されます。
■さらにチェック!地方自治体独自の上乗せ給付金
前述の国の就学支援金や高校生等奨学給付金に加えて、地方自治体によっては、独自の給付金制度を設けて、学費の負担をさらに軽減している場合があります。
これらの制度は、自治体によって対象者や支給額、申請方法などが大きく異なります。
確認方法
自治体によっては、国の制度に上乗せして独自の給付金制度を設けている場合があります。
お住まいの自治体にも給付金の上乗せがあるかもしれません。ぜひ一度確認してみてはいかがでしょうか?
■その他の学費関連の支援制度
上記以外にも、学費の負担を軽減するための支援制度が存在する場合があります。
日本政策金融公庫が提供する教育ローンは、入学金や授業料だけでなく、在学に必要な様々な費用に利用できます。低金利で利用できるため、民間の教育ローンと比較して返済負担を抑えることができます。
多くの大学や専門学校では、独自の奨学金制度を設けています。成績優秀者向けの奨学金や、経済的に困窮している学生向けの奨学金など、様々な種類があります。進学を希望する学校のウェブサイトや学生支援課で確認してみましょう。
民間の企業や財団などが、独自の奨学金制度を提供している場合があります。これらの情報は、インターネットの奨学金情報サイトなどで探すことができますので、ぜひ確認してみてくださいね。
この記事のまとめ|学費無償化を最大限活用するために
2025〜2026年にかけて、高校・大学の学費支援はこれまで以上に拡大し、特に多子世帯や中間所得層でも利用できる制度が増えています。
この記事で紹介したように、
- 高校の無償化(就学支援金)
- 大学の無償化(修学支援新制度)
- 多子世帯の所得制限撤廃
- 公立・私立の支援額の違い
- 自治体独自の補助
- 奨学金との併用
など、複数の制度を組み合わせることで、家計の負担は大幅に減らせます。
とくに大切なのは、
「自分は対象なのか?」
「いくら支援されるのか?」
「いつ・どうやって申請するのか?」
この3つを正確に知ることではないでしょうか?
制度は毎年アップデートされるため、最新の情報を確認しながら、使える制度はどんどん活用してていきましょう!
(執筆者:yuffy)



