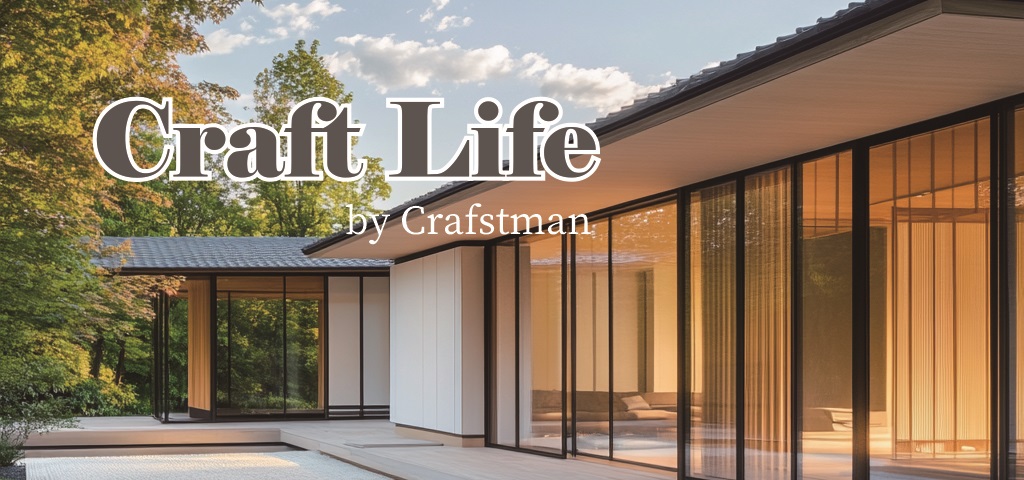「耐震」の説明をする前に、「木材の質」及び「土台を含めた躯体全体」について解説します。
まず「土台」ですが、耐久性があって腐りにくいことと、シロアリの被害を受けにくいことが求められます。「仕様書」には、腐りにくい耐腐朽性(たいふきゅうせい)とシロアリに強い防蟻性(ぼうぎせい)が高い材料として「ヒノキ、ヒバ、米ヒバ」などが紹介されています。
一定以上の耐久性を持つ木材のことを、「D1材」と呼びます。また、工場で薬液を加圧して注入された木材を使う場合もあります。
あと木材には「よく乾燥したものを使う」ということが仕様書には書かれています。
よく乾燥した木材のことをKD材(Kiln Dried材)と呼びます。
これの反対はAD材(Air Dry 自然乾燥材)・グリーン材(未乾燥木材)と呼ばれます。
含水率を下げると木は安定し、強くなり、耐久性も増します。乾燥材の含水率は20%程度と言われています。製材前の木材の含水率は50~60%程度ありますが、 製材店や工務店で寝かして保管・乾燥させることによって、約20%程度まで含水率が下がります。
まとめると
人工乾燥材 ── Kiln Dried材
自然乾燥材 ── Air Dry材
未乾燥材 ── Green材(グリーン材)
です。
木材の表示の中で、D25・D20・D15などの表記を見かけることがありますが、
これらは、それぞれ含水率が「25%以下」「20%以下」「15%以下」という意味です。
●すまいの性能 基礎知識
https://sumai-sankou.com/seinou-kiso/kigou-KD.htm
土台の上に、木材の骨格を組み込んでいく工事を「大工工事」と呼びます。
いわゆる大工さんの工事です。
木造工事には「在来軸組み工法」と「枠組み壁工法(ツーバイフォー)」がありますが、
ここでは「軸組み工法」のほうで説明します。
そのプロセスは、「軸組」「床組み」「小屋組み」に分かれます。
柱を縦横に組むのが「軸組」、1階床材・2階床材などを組み込むのが「床組み」、
屋根材を組んでいくのが「小屋組み」です。
木材は、その使われ方によって、名称が異なります。
土台から垂直方向に立てるのが「通し柱」「管柱(くだばしら)」で、
水平方法に使われるのを「梁(はり)」や「桁(けた)」と言います。
具体的には「胴差(どうさし)」「床梁(ゆかばり)」「軒桁(のきげた)」「小屋梁(こやばり)」などが、水平に架け渡して組まれる木材です。これら「大きな木材」をまとめて「構造材」といいます。
「羽柄材(はがらざい)」とは、構造材を補う材料や下地材のことです。
間柱(まばしら)筋交い(すじかい)、根太(ねだ)、垂木(たるき)などが羽柄材です。
木材を組んだ「イラスト」をずーっと見ていると、垂直か水平か、構造材か羽柄材か、
木材の使われ方によって、名称に特徴があることが分かります。
ところで「床束」「小屋束」というものがありますが、「束」が付いている材料は
「垂直材」となります。
ちなみにこの見積もりでは、「床束」は木材ではなく鋼製の「束」を使用しています。
「木材」同士の接合方法には、「継ぎ手」と「仕口」という二つのやり方があります。
部材を同じ長さ方向に接合する部分を「継ぎ手」といい、イラストで示すのが一番分かりやすいですが、「腰掛け蟻継ぎ」「腰掛け鎌継ぎ」などがあります。「ねじれ」や「引っ張り」などに
対応できるようになっています。
なぜ「蟻(あり)が出てくるの?」と思われた方もいるかもしれませんが、
「蟻の頭の形に似ているから」というのが由来のようです。
ちなみに「鎌継ぎ」の「鎌」は、蛇の鎌首に似ているからそう呼ばれるようになったようです。
建築部材には、他にも「ネコ土台」など、身の回りの生き物が付いた用語がたくさんあって
興味深いです。
「仕口」は、部材が直角に接合される場合の「接合部分」の呼び方です。
これは、木材の断面にに凸の形をした「ほぞ」を作り、土台などに凹の形をした「ほぞ穴」を
作り直角にドッキングすることです。「ほぞ差し工法」とも呼びます。
ほぞには「短ほぞ(たんほぞ)」「長ほぞ(ながほぞ)」があります。
次に木材のサイズですが、柱の断面は「10.5㎝×10.5㎝」が多く、土台は「10.5㎝四方」または
「12㎝四方」が多いようです。2階の「床梁」で使われる梁の断面は、もう少し大きく「12㎝×24㎝」
のものが多く使われるようです。
「仕様書」に掲載されている調査結果によると、「通し柱」のサイズは10年以上前は「12㎝角」が
7割以上でしたが、近年は「10.5㎝角」もしくは「通し柱はない」という回答も増えています。
これは「構造的な理由」によるものと思われます。
このように柱を立て、胴差、床梁を組み、2階の軒桁、小屋梁を組むまでは、1日で一気に組み上げる
ことが多いです。この一連の作業のことを「建て方」もしくは「建て前」と呼びます。
ここで「構造上の強度を増す」補強材について説明します。
まず、土台から斜め方向に鉛直に立てる「筋交い」です。
「筋交い」を「X」の形のようにたすき掛けにすると強度が増し、構造用合板を立てると、さらに
外的な力に対する耐性が増します。
同じ目的で、水平方向に付ける補強材を「火打ち」と言います。土台のコーナーに付けるものを「火打ち土台」、
「梁」のコーナー部に付けるものを「火打ち梁」と言います。
どちらも、地震や台風時に発生する水平力による変形を防止する役目があります。
建築基準法で定められている耐力壁の強さのことを「壁倍率」と言います。
厚みが15センチで幅9.0センチの「筋交い」を入れた壁を「壁倍率1.0」として基準にしています。
「片筋交い」「たすき掛け筋交い」「構造用合板」の組み合わせによって、「壁倍率」はさらに大きくなります。
壁倍率の上限は5.0です。数値が大きくなるほど性能が高い壁ということになり、耐震性能が高くなります。
「筋交い」や「構造用合板」によって、その部分の強度が増すということは分かっていただけるかと思いますが、
建物を「四方面」から見た時のバランス、「1階と2階」の入れ方がどうなっているかが重要です。
●不良在来木造構造現場の例。筋交いの向き無茶苦茶。上階に柱と筋交いがつき下階に柱がない場所の梁が細い
https://shinkahousinght.at.webry.info/201608/article_7.html
●木造住宅の耐震設計のポイント
https://k-inoue.ohotk.com/taishin.htm
構造用合板とは、薄い板を重ねて接着剤で貼り合わせたものです。元は、木材を薄くむいた
1.0ミリ~5.5ミリの単板を繊維方向に直交させて、奇数枚で貼り合わせます。3枚重ね合わせると
1枚目と3枚目が同じ繊維方向になっていて、表と裏を見比べると繊維が同じ方向、3枚なので
強度が増すというわけです。
構造用合板には、3枚・5枚・7枚・9枚合わせがあります。
合板は、使用される部位や用途により多くの種類があります。床や壁などで「構造的に」使われる
ものを「構造用合板」と呼びます。
構造用合板の品質は、JASに規定されており、1級と2級があります。
2級は木造住宅の耐力壁、床の下地、屋根の下地など、いわゆる「下張り」に使われるものが対象です。
1級は、さらに所定の強度試験に合格したものになります。
次に「断熱工事」「気密工事」について説明します。
よく「高気密高断熱」と言いますが、この二つはセットで力を発揮します。
断熱とは「室内の温度が外気温に影響されないようにさえぎる」ことで、
気密とは「空気の流れを止めて室内の温度を保つ」ことです。
夏に「冷房を入れているのに、どこかから熱気が入っているような気がする」のは、
「隙間があるから」で、気密性が不十分なのかもしれません。
また、冬場に暖房を入れていても、「下から冷気を感じる」のは断熱性が不十分なのかも
しれません。
「空気や熱の流れ」というのは、抽象的に聞こえるかもしれませんが、
「断熱性」も「気密性」も数値化して測ります。
まず、断熱性は「Ua値(ユーエーチ)」というもので測ります。
外と室内の気温差があったときに、これは「1㎡あたり何wの熱が逃げるか」という
「熱損失量」のことです。
単純に言うと、熱が伝導しにくい「窓(開口部)」「壁(外壁)」「天井(屋根)」「床(基礎)」
にすれば、「Ua値(ユーエーチ)」は低くなります。
これは現場で測定するのではなく、「サッシの種類」「ガラスの種類」「断熱材の種類や厚み」
「断熱材の施工方法」によって、設計の時点で計算できるものになります。
なので、「床・壁・天井」の断熱材はネオマフォームや硬質ウレタンフォーム、
サッシはアルミ樹脂・トリプルガラス(Low-E ガラス使用)にすれば、断熱性能はかなり高く
なります。
このサイトでは、「地域4」で「Ua値が0.5くらい」になるような断熱材・サッシを選択して
います。ちなみに、地域4とは、関東よりも少し寒い地域になります。
現在の省エネルギー区分は、北海道を1、沖縄を8として、全国を「8地域」に分けています。
Youtube動画などでは、単純に「都道府県名」だけを表示していることがありますが、
「仕様書」ではもっと厳密に分類されており、たとえば「山梨県」でも「忍野村」はかなり寒い「地域2」になっていますし、
東京でも「八丈町や小笠原村」は暖かいほうの「地域7」となっています。
●断熱地域区分
https://www.achilles.jp/product/construction/insulation/knowledge/chiikikubun/
次に「気密」ですが、「C値(シーチ)」という尺度で測ります。
これは、北海道でも九州でも同じ基準で、1㎡あたり「すき間の面積がどれくらいあるか」を
見ます。
たとえば、例えば「C値1.0㎠/㎡」だと、1平方メートルあたり「1センチ角」のすき間がある
ということになります。
「C値0.5㎠/㎡」だと、1平方メートルあたり「0.7センチ角」のすき間があるということになります。
「C値」は低いに越したことはありませんが、緻密で厳格な現場施工が求められます。
「すき間がない」ということは、いわゆる密閉された状態ですので、断熱効果が高くなるのは
言うまでもありません。
本サイトでは、「C値0.5㎠/㎡」を目指せる基準を設定していますが、
これは「技術力と施工方法」により、差が出ますので、住宅メーカーに確認してみてください。
「気密」については、「換気設備」とも関わってきますので、
衛生工事のところでも説明します。
【工事の手順】(断熱工事・気密工事)
1.(基礎:内側)硬質ウレタン、グラスウールなど
2.(基礎:外側)硬質ウレタン、グラスウールなど
3.(壁:内側)硬質ウレタン、フェノールフォーム、グラスウール
4.(壁:外側)外断熱の場合:フェノールフォームなど
5.(天井)高性能グラスウールなど