パートナーの帰りが毎日遅い
休日はパートナーが不在でほとんど家にいない
単身赴任や離別など、さまざまな理由でひとりで育児をしている方もいらっしゃるでしょう。
ワンオペなうえに年子の子どもをもつご家庭では、「赤ちゃんが2人いるようで大変」と感じられる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、ワンオペ育児が大変な理由や乗り切るコツを解説します。
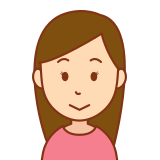
夫が泊まりのある勤務で、週3回丸一日ワンオペで年子育児をしている筆者が経験も交えて解説します!
ぜひ本記事を参考に、年子のワンオペ育児を乗り切るヒントを見つけてください。
年子ワンオペが大変な理由
母親か父親、どちらか片方のみが育児するワンオペ育児。年子のお子さまを2人見る場合、肉体的にも精神的にも大変ですよね。
生活のお世話や遊びたいという欲求に応えながら、家事もすべて一人で対応しているとあっという間に1日が過ぎてしまいます。
年子のワンオペ育児が大変に感じる理由を洗い出してみていきましょう。
上の子もまだお世話に手がかかる
下の子が生まれて間もなくは、上の子も1歳で赤ちゃんが2人いるような状態です。
ご飯の介助やお着替え、排泄などお世話にまだまだ手がかかります。特に生まれてすぐは下の子の授乳も頻回で、まだ甘えたい時期の上の子をつい我慢させてしまうシーンもよくあるのではないでしょうか。
このように一人で対応しきれない時に大変さを痛感するでしょう。
生活リズムが合わず親が体力限界になる
下の子の授乳や夜泣きにより睡眠不足の中、日中は上の子の遊びに付き合い毎日疲れがたまるのではないでしょうか。
同じタイミングで泣きだしたり、これしてあれしてと言われることが1日に何回もあります。それらに応えながら日々のタスクをこなすだけで、体力が消耗するでしょう。
寝不足や疲れがたまり、イライラしたり、体調不良をおこしたりすることで、子どもに優しくできないと悩まれる方もいらっしゃいます。
完璧に意思疎通ができない
下の子が生まれてすぐの頃、上の子は発語が増えてくる段階かもしれません。赤ちゃんの頃に比べて意思疎通ができるようになったとはいえ、正確に欲求をくみ取れないこともあるでしょう。
上の子のまだ曖昧な言葉での要求や、下の子の泣き声や態度から何をして欲しいのかを察するだけでも頭を使います。2人同時に何かしてほしいそうにするときは、どちらを優先すべきか状況を見て対応するため、常に頭をフル回転させなければいけません。
完璧な意思疎通ができないもどかしさは、精神的な負担につながります。
年子ワンオペ育児を乗り切るコツ
子どもたちが、自分で身の回りのことができるようになるまでは特に年子育児の大変さが身にしみます。
日々のタスクをどれだけ効率良くすすめて、自分の体力を温存するかが勝負です。ここからは、ワンオペでの年子育児を乗り切るコツを紹介します。
タイスケジュールの例と優先順位の考え方
年子ワンオペ育児のタイムスケジュールを紹介します。

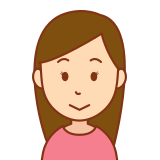
こちらは筆者が実際に経験したタイムスケジュールです。この通りにいけばお昼寝の時に自分時間が確保できます!
ただしタイムスケジュールは理想のケースで、いつもこの通りにはなりません。
おすすめは起きる時間と寝る時間を決め、寝る前のルーティーンを決めることです。
起きる時間を決めることで、自然に寝る時間も整ってきます。寝る前のルーティーンを決めれば、スムーズな入眠につながります。
家事は完璧にこなすことにこだわらず、最低限やらなければいけないことを優先するのも一つの手段です。
余裕があれば、タスクを洗い出し「やらなければいけないこと」「できるといいこと」「やらなくてもいいこと」に分類し、優先順位をつけるといいでしょう。
家事・育児の仕組みづくり
家事・育児に関する決まった作業は仕組み化するのがおすすめです。
- 献立は1ヶ月分決めておき毎月くり返す
- 時間があるときに食事の下ごしらえをして冷凍しておく
- 「ついで掃除」の習慣化
- おもちゃは簡単に片付けられるようにする
- 使う場所にものを収納する
- 時短家電を活用する など
献立をまとめて考えたり、下ごしらえを一気にしたりすることで、料理をする際に楽です。
トイレを使ったら掃除する、最後にお風呂を使った人がついでに掃除までするなど、何かのついでにこまめに掃除しておくのもおすすめです。
また、毎日おもちゃの片付けをするのが大変という方もいらっしゃるでしょう。子どもが小さいうちは、簡単に片付けられるようにするのがおすすめです。おおきなかごなどを用意してひとまとめに片付けられるようにすると、子どもも迷わず片付けられます。
頼れる支援・サービスまとめ
年子のワンオペ育児が大変な時は、行政の支援や民間のサービスを活用しましょう。
| 支援やサービス | ポイント |
| ファミリーサポート | 地域住民の協力により安価でサポートを受けられる 事前に登録や面談が必要 |
| 一時預かり | 保育施設などで一時的に子どもを預けられる 事前登録や予約が必要 年齢や時間に制限があることも |
| 地域の子育て支援センター | 育児相談や親子の交流の場としても利用可能 無料なケースも多い 託児サービスはないことがほとんど |
| ベビーシッター | 自宅で個別に対応してもらえる 費用は高め 信頼できる業者選びが重要 |
| 家事代行サービス | 掃除・洗濯・料理などを依頼でき育児に専念できる サービス内容や時間帯で費用が変動 |
| 宅配サービス | 食材や日用品の買い出しの負担を軽減 配送料がかかる 量のわかりづらさ、鮮度に注意 |
下の子が小さいうちは、児童館や子育て支援センターなどの屋内施設が過ごしやすくておすすめです。職員の方や他のママと話すことで気分転換にもなるでしょう。
便利グッズや時短アイテムの活用
年子のワンオペを楽にするには、便利グッズや時短アイテムを活用することが重要です。ここからは、おすすめのアイテムを紹介します。
バスローブ
年子のワンオペで大変なタスクのひとつがお風呂です。子どもたちのケアを優先して、自分のことがあとまわしになる親御さんには、こちらのバスローブがおすすめです。こちらはレディースですが、頭からかぶるだけでさっと着られるので、ひとまずかぶっておけば子ども達のケアに専念できます。
圧縮トラベルポーチ
年子の子どもたちとおでかけする際、おむつがかさばって荷物が増えるということもありますよね。そこでおすすめなのがこの圧縮トラベルポーチです。旅行で洋服などを圧縮するのに使えるポーチですが、おむつを入れて持ち運ぶことも可能です。子どもの着替えなども一緒に入れられるので、荷物がコンパクトになります。
キッチンばさみ
料理の時間短縮におすすめなのがこのキッチンばさみです。少量だけ切りたい、肉を切りたいという時にも使えるので、包丁とまな板を洗う手間が減らせます。子どものご飯を小さくしたいときにも便利。分解して洗えるので、清潔を保てるのもポイントです。
住所印
子どもが生まれると、予防接種、役所や保育園・幼稚園など各種手続きで、住所を書く機会が増えますよね。こちらの住所印をひとつ持っておくと、圧倒的に時間眼宿につながります。選ぶ際は、予防接種の問診票の枠のサイズに合うか、確認するといいでしょう。
一人でがんばりすぎないで休むことも大切
年子の子どもたちをワンオペでみていると、何でも自分で対応しなきゃと頑張りすぎてしまうこともあるでしょう。
親もたまには休んで健康でいることで、子どもたちも安心してすごせます。がんばりすぎずに、家族や支援やサービスを頼ることも大切です。
頼れるものは活用しながら、子どもたちと一緒に成長していきましょう。
(執筆者:宮関あゆみ)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4803169d.e73780d1.4803169e.0b09f1af/?me_id=1190468&item_id=10176464&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshirohato%2Fcabinet%2F000910%2Fc1320t201.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48031760.6127eecb.48031761.0b1c16bb/?me_id=1386561&item_id=10000777&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fownlife%2Fcabinet%2F07587831%2F10114948%2F11043344%2F01a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4803184d.7e13ca55.4803184e.febd0673/?me_id=1413163&item_id=10000072&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fexception5251%2Fcabinet%2F11219683%2F11219688%2Fdiscount80%2Fc-00030.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48031952.393f4d46.48031953.b7944149/?me_id=1228354&item_id=10006125&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbugyo%2Fcabinet%2F00587980%2Fs0560_1_sum_4-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

