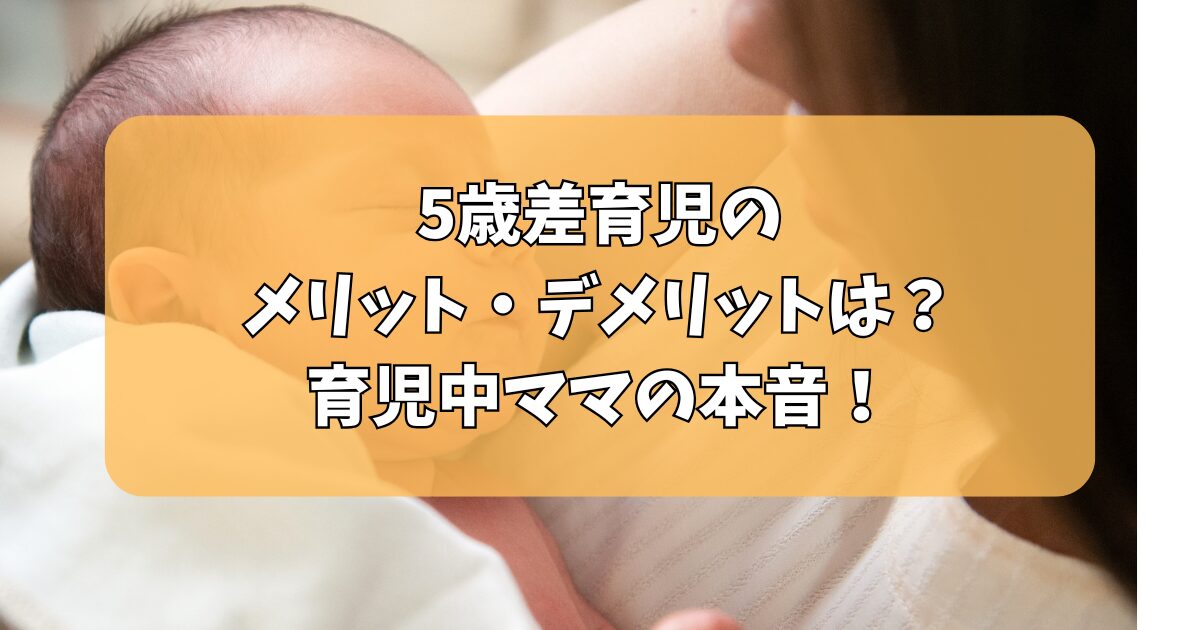「年が離れたきょうだいって育てやすいの?それとも大変?」
長女と5歳差で2人目の次女を妊娠したとき、私もそんなふうに悩んでいました。
「ちょっと年齢が離れすぎじゃない?」なんて、周りから言われることもありました。
でも実際に育ててみると、5歳差育児には意外なメリットがたくさん!
もちろん大変なこともありますが、嬉しい発見や助けられる場面もたくさんあります。
この記事では、5歳差姉妹を育てる私の体験をもとに、年の差育児のメリットと大変だったこと、そして乗り越えるための工夫をご紹介します。
5歳差になったわけ
長女を出産し、1年で仕事復帰した私は、当初「3歳~4歳差くらいで2人目を」と考えていました。
ですが、実際には小さな子どもを育てながらの共働き生活は想像以上に大変。ヒーヒー言いながら過ごすうち、あっという間に時間が過ぎてしまい、気づけば4歳差ギリギリの年齢に。
長女もだいぶしっかりしてきたので妊活を始めましたが、すぐには授かれず、最終的に5歳差で妊娠が判明しました。
もちろん周囲からは祝福されましたが、友人や親族の多くは2〜4歳差でのきょうだい育児。5歳差は少数派だったこともあり、「どんな感じになるんだろう?」という不安も正直ありました。
5歳差育児のリアルなメリット

長女が5歳を迎える少し前に次女を出産し、5歳差での二人育児がスタートしました。
実際に始まってみると、5歳差育児は想像していたよりもずっと穏やか。
「5歳差で本当によかった」と感じる場面がたくさんありました。
ここでは、実際に感じたメリットをご紹介します。
赤ちゃんとじっくり向き合える時間がある
次女を出産したのは、長女が年中(4歳)だったころ。すでに幼稚園に通っていたため、日中は赤ちゃんのお世話に集中できる時間が確保できました。これはとても大きなメリットです。
特に新生児期は、夜間授乳や夜泣きでほとんど眠れない日々が続きます。
そんななか、上の子が日中いないことで、赤ちゃんと一緒にお昼寝して体力を回復することができました。
もしこれが2〜3歳差だったら、日中も上の子のお世話が必要で、昼寝どころではなかったと思います。
自分の体力を保ちつつ、穏やかな気持ちで次女と向き合えたのは、5歳差ならではの良さでした。
おもちゃや服など、お下がりが使える
5歳差があると、上の子が使っていた育児グッズや洋服、おもちゃなどをスムーズにお下がりとして使えるのも大きなメリットです。
わが家の場合も、ベビーバスや抱っこ紐、ベビー布団などの大物はもちろん、スタイや肌着、ロンパースなどもきれいに保管していたため、次女にも十分使えました。
また、5年経っても状態のよいおもちゃや絵本も多く、新たに買い揃えるコストを抑えることができました。
ただ、完全に同じものを使うのではなく、次女専用の新しい洋服やおもちゃも少しだけ用意。上の子が「これは妹のもの」と認識できることで、お下がりばかりという印象を持たずに済み、姉妹それぞれにとって気持ちよく使える工夫になりました。
上の子がしっかりしているから、赤ちゃんのお世話を手伝ってくれる
これは子どもの性格にもよると思いますが、長女は赤ちゃんの誕生をとても楽しみにしていて、生まれてからも沐浴やミルクなどを「やりたい!」と言って積極的に手伝ってくれました。
もしこれが2~3歳差だったら、どちらもまだまだ赤ちゃんのような時期で、上の子がイヤイヤ期真っ最中という可能性も。
きっと毎日がカオスだったと思います…。
その点、上の子が「育児の戦力」として頼れる存在だったのは、本当に助かりました。
赤ちゃん返りが無かった
こちらも性格によるとは思いますが、長女は赤ちゃん返りがほとんどありませんでした。
正直、夫の実家にとっては「初の女の子の孫」、私の実家にとっては「初孫」という存在だったため、長女はずっと蝶よ花よとちやほやされて育ってきました。
だからこそ「きっと赤ちゃん返りがひどくなるだろうな…」と身構えていたのですが、拍子抜けするくらい平常運転でした(笑)。
もしかすると、長い間愛情を一身に受けてきたことで、心が満たされていたのかもしれません。
1年だけ小学校がかぶる
5歳差の場合、上の子が小学校6年生のときに、下の子が1年生。
ちょうど1年間だけ、小学校生活が重なります。
初めての学校生活、登下校や教室での不安…。
そんな1年生の心細さを、最高学年であるお姉ちゃんがそばで見守ってくれるというのは、親にとっては心強い限りです。
「一緒に登校してくれるかな?」という希望も込めて(笑)、今からその1年を楽しみにしています。
5歳差育児の大変だったこと
メリットの方が大きいと感じた5歳差育児ですが、もちろん大変なこともあります。
生活リズムがまったく違う(赤ちゃんの夜泣き×上の子の登園準備)
赤ちゃんは昼夜関係なく泣くし、上の子は朝から元気いっぱい。
特に新生児期は、夜間授乳でほとんど眠れないのに、朝は長女の登園準備で6時起き……という日々が続き、とにかく体力勝負でした。
「やっと寝た!」と思ったタイミングで上の子が起きてきたり、夜泣き対応で寝不足のまま送り出したりと、リズムの違いに振り回される毎日。
朝は特にバタバタで、「あと10分寝かせて……」と何度思ったことか分かりません(笑)。
上の子の習いごとや園行事との両立が大変
長女は年中~年長の間に妹が生まれたので、発表会や遠足、参観日など、行事がたくさん。
そのすべてに、抱っこ紐に赤ちゃんを入れた状態で対応しなければなりません。
タイミング悪く授乳の時間と送迎がかぶったり、やっと寝てくれた直後にお迎え時間になったりと、常に分刻みのスケジュール。
「もうひとり自分がいたら…」と本気で思ったことも何度もあります。
家族のお出かけ先や遊び方を合わせるのが難しい
上の子は公園で思いきり走り回りたい年齢、でも下の子はまだ抱っこ期。
お出かけ先の選び方や、レジャーのスタイルに悩む場面も多かったです。
例えば「遊園地に行きたい!」と言われても、ベビーカーでの移動や授乳スペースの確保が必要だったり、昼寝の時間とかぶったり。結局下の子はずっとママと待機…なんてことも。
とはいえ、これは成長とともに少しずつ解消されていくもの。
「今はこういう時期」と割り切って、上の子の希望をできるだけ叶えつつ、無理しない工夫を心がけました。
乗り越え方と工夫したこと
上の子との時間を意識して確保する
下の子が生まれると、どうしてもお世話にかかりきりになってしまいがち。
でも、上の子にとっても「ママを取られた」という寂しさを感じやすい時期です。
そこで意識的に、上の子と二人きりで過ごす時間を作るようにしました。
寝かしつけのあとは絵本を読んだり、登園前の朝の10分を「おしゃべりタイム」にしたり。
ほんの短い時間でも、「ママはちゃんと見てくれている」と感じられるよう心がけました。
すべてを完璧にやろうとしない
「お出かけもしてあげたい」「行事もちゃんと参加したい」「家も片づけたい」――
そんな気持ちでいっぱいいっぱいになる日もありました。
でも、「今日は無理そう」と思ったら割り切って家で過ごしたり、夫に頼ったり、便利なサービスに頼ったり。
歳が近いきょうだい育児と比べて余裕のある5歳差とはいえ、子ども2人の育児はやっぱり大変です。
だからこそ、「やらなきゃ」に縛られすぎないことが、結果的に家族みんなの笑顔につながると感じました。
まとめ:5歳差育児は最高!
もちろん大変なこともありますが、私にとって5歳差育児はメリットの方がずっと大きかったと感じています。
正直なところ、キャパシティが小さい私は、2〜3歳差だったらきっとパンクしていたと思います(笑)。
もちろん、子どもは授かりもの。何歳差がベストかは、家庭ごとに違うものです。
でも、もし「5歳差ってどうなんだろう?」「もう遅いかな…」と迷っている方がいたら、こんな形の育児もあるよ、という一つの参考になれば嬉しいです。
暮らしのヒントがもっと見つかる「Craft Life」
部屋づくりのヒント、子どもとの暮らしをもっと楽しむアイデア、
そして、慌ただしい日々の中でも“ほっとひと息”つける時間の作り方——。
そんな“小さな工夫”が、毎日の家事や育児を驚くほどラクにしてくれます。
「Craft Life」では、子育て中のママ・パパに寄り添いながら、
家族みんなが心地よく暮らせるアイデアを日々発信しています。
たとえば…
- 片づけが自然と続く“しくみ”のつくり方
- 子どもの「やりたい!」を引き出す収納の工夫
- 家事をラクにする習慣の整え方 などなど。
読みやすく、すぐに実践できるヒントが満載です。
登録無料!暮らしの“ミニ知恵袋”が届きます
Craft Lifeのメルマガでは、忙しい毎日を助ける暮らしの工夫をギュッと凝縮してお届け。
すきま時間にサッと読めて、明日から役立つ情報ばかりです。
- 買ってよかった育児グッズ
- 忙しい日のための時短アイデア
- 赤ちゃんが生まれたらもらえるお金の話
登録はもちろん無料。
あなたの暮らしがもっとラクで、もっと楽しくなるヒントを受け取ってみませんか?
▼メルマガ登録はこちらから▼
(執筆者:AKKA)