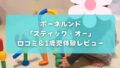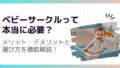塾や習い事の帰り道、子どもがひとりで歩く時間って、どうしても心配になりますよね。特に夜道や人通りの少ない道を通るときは、「ちゃんと無事に帰ってこられるかな…」と、親として気がかりになるものです。
実際、地域によっては不審者の情報や声かけの事案も報告されていて、日頃から防犯への意識を持っておくことが大切だと感じます。
そこで今回は、「塾や習い事の帰り道に役立つ防犯・安全対策」を、すぐに取り入れられる工夫とともにまとめました。
見守りアプリや防犯ブザーなどのツールはもちろん、子ども自身が身につけておきたい習慣、そして保護者や地域の大人が今日からできるサポートの方法まで、幅広くご紹介します。
◆「帰り道の防犯」なぜ重要?

子どもがひとりで行動する「帰り道」は、家庭や学校の目が届きにくい時間帯。
特に塾や習い事が終わる夕方以降は、暗くなって視界も悪くなり、人通りも少なくなることで、不審者が声をかけたり後をつけたりするリスクが高まります。
実際、警察庁の犯罪統計でも、声かけ事案や不審者の情報は放課後から夜にかけて多く報告されています。
「うちの子は大丈夫」と思っていても、狙われやすい環境は日常の中にひっそりと潜んでいるんです。
だからこそ、「帰り道」に特化した防犯対策を、あらかじめ家庭で整えておくことが、子どもの安全を守る大切な鍵になります。
♢塾や習い事の時間帯に潜む危険とは?
塾や習い事の終了時間は、ちょうど夕暮れから夜にかけての「犯罪リスクが高まる時間帯」。いつも以上に注意が必要です。
このように「暗さ・人通りの少なさ・注意力の低下」が重なることで、子どもが危険に巻き込まれるリスクは高まります。
だからこそ、家庭でできる防犯の工夫を、日常の中に取り入れていくことが大切なんですね。
♢狙われやすい子どもの特徴とは?
不審者が子どもを狙うとき、実は「声をかけやすい状況」や「接触しやすいタイミング」を見極めていると言われています。
特に、次のような特徴がある子どもは、ターゲットになりやすい傾向があるため、注意が必要です。
こうした行動は、相手に「接触しやすい」と思わせてしまうきっかけになります。

だからこそ、家庭で日頃から「どんな道を通る?」「今日は誰と帰る?」といった会話を重ねておくことが大切なんですね。
複数の帰宅ルートを用意したり、時には親子で一緒に歩いてみたりすることで、「狙われにくい工夫」が自然と身につきます。
◆子どもが「自分でできる!」安全を守る行動習慣とは?
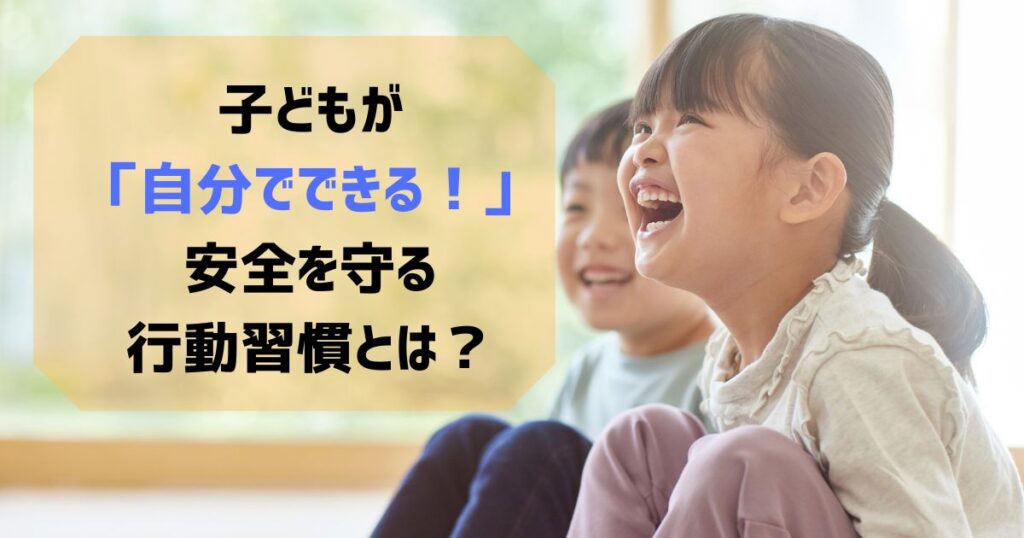
防犯の基本は、子ども自身が「危ないかも」と感じたときに、ちゃんと避ける行動ができること。
もちろん、保護者や地域の見守りも大切ですが、実際に帰り道でどう動くかを判断するのは、子ども本人です。
だからこそ、日頃から「こんなときはどうする?」というルールを親子で共有しておくことが大事ですよね。いざというときに自然と体が動くように、普段の帰宅時にも少しずつ実践していけると安心につながります。
ここでは、家庭で伝えておきたい「安全な行動習慣」を整理しました。
親子で話し合いながら、ぜひ日々の暮らしに取り入れてみてくださいね。
①安全な道を選ぼう!〜通る道の選び方と注意点〜
「近いからこの道でいいや」と、つい距離だけで帰り道を選んでいませんか?
でも、子どもの安全を考えるなら、「近さ」よりも「安心できる道」を選ぶことが何より大切です。
親子で一緒に、こんなポイントを確認してみましょう。
また、毎日同じ道ばかり通っていると、不審者に行動パターンを読まれてしまうことも。

できれば複数のルートを用意して、「今日はこっちの道で帰ろうか」と親子で話しながら選べると、さらに安心ですね。
②一人歩きのNG行動はこれだ!〜イヤホン・スマホ歩き〜
帰り道でのちょっとした行動が、思わぬ危険につながることもあります。特に注意力が下がっていると、不審者に「隙がある」と思われてしまうことも。
お子さんがこんな様子で歩いていたら、ぜひ一度、危険性を伝えてみてくださいね。
「両手は空けて、前を見て歩く」——これが帰り道の基本です。

ただ言葉で伝えるだけじゃなくて、実際の帰宅時に「今日はちゃんと前見て歩けた?」なんて声をかけてみると、子ども自身も意識しやすくなりますよ。
③不審者に出会ったときはどうする?〜対応をルール化!〜
もしも帰り道で、知らない人に声をかけられたり、後をつけられたりしたら——そんな「万が一」に備えて、家庭でルールを決めておくことがとても大切です。
いざというときに迷わず動けるように、こんな行動を親子で話し合っておきましょう。
さらに、家庭で練習をしてみるのもおすすめです。

「もしこういう場面だったらどうする?」と一緒に考えてみることで、子ども自身の判断力も育っていきますよ。
◆子どもの安全を守る!おすすめ防犯グッズ・ツール

帰り道の安全を守るには、子ども自身の注意力だけでなく、「防犯グッズ」や「見守りツール」の力を借りるのも有効です。特に小学生の場合は、使い方がシンプルで、いざというときにすぐ行動できるものを選ぶのがポイント。
ここでは、持たせておくと安心につながるアイテムやツールをご紹介します。
♢小学生でも使いやすい防犯ブザー・ライト
まず基本となるのが「防犯ブザー」。ボタンを押す、ひもを引くなどの簡単な動作で大きな音が鳴り、周囲に助けを求めることができます。
子どもが無理なく使えるものを選んでみてください。電池切れに気づかないこともあるので、定期的な作動チェックも忘れずに。
♢GPS端末の活用
最近では、子どもの位置情報を確認できるGPS端末を活用するご家庭も多いようです。
GPS端末には上記ような機能があるのが特徴で、離れていても「今どこにいるか」がわかる安心感があります。特に習い事が夜遅くなるご家庭では、心強い味方になりますね。
GPS端末には、音声のやり取りができるもの、防犯ブザー機能が付いているものなど、種類も豊富です。ぜひ、ご家庭に合ったものを選んでみて下さいね。
♢親子でチェックしたい!防犯アプリの機能
スマホを持ち始める高学年〜中学生には、防犯アプリの導入もおすすめですよ。
▪️ワンタップでSOSを発信できる機能
▪️現在地を保護者に共有できる機能
▪️地域の不審者情報や避難所情報を通知する機能
これらを備えたアプリは、もしものときの連絡手段として役立ちます。
ただし、アプリは「入れて終わり」ではなく、使い方を理解していないと意味がありません。
ぜひ導入時に、親子で一緒に操作方法を確認してみてくださいね。
◆親ができる!送迎・見守りの3つの工夫

子ども自身が防犯意識を持つことは大切ですが、保護者のちょっとしたサポートで、帰り道の安全度はぐんと高まります。
特に小学生や、夜遅くまで習い事があるご家庭では、送迎や見守りの工夫が「狙われにくい環境づくり」に直結します。
ここでは、家庭で取り入れやすい3つの工夫をご紹介します。
1.時間やルートを決めて迎えに行く
毎回の送迎は難しい場合でも、
「この曜日は必ず迎えに行くよ」
「この場所で待ち合わせしよう」
といったルールを決めておくだけでも、子どもにとっては大きな安心につながります。
また、同じ時間・同じ道ばかりだと行動が読まれやすくなるため、あえて帰り道を変える工夫も効果的ですよ。
親が迎えに行けないときは、祖父母や地域の知人、ママ友などに協力をお願いするのもひとつの方法です。
2.友達や兄弟と一緒に帰る「グループ帰宅」
一人で歩く時間を減らすことは、防犯の基本。 友達や兄弟と一緒に帰る「グループ帰宅」は、不審者への心理的な抑止力にもなります。
習い事の保護者同士で「この曜日は一緒に帰らせよう」などと声をかけ合っておくと、自然な形で実践できますね。
子ども同士も安心できるので、親子ともに心強い方法ですね。
3.家族内での連絡ルールを決めておく
帰り道の安全を守るには、家族間で連絡ルールを作っておくことも大切です。
- 家を出るときに「今から行くよ」と連絡する
- 到着したらLINEでスタンプを送る
- 予定より遅れるときは必ず電話する
など、家庭ごとのルールを決めておくことで、万が一のときにも早めに気づくことができますね。
スマホを持っていない場合は、キッズ携帯(スマートウォッチ)やGPS端末を活用するのもおすすめ。子どもが「ちゃんと見守られている」と感じられることで、安心して行動できるようになりますよ。
◆地域や社会の力を借りる!知っておきたい防犯対策

子どもの安全を守るには、家庭だけでがんばるのではなく、「地域や社会のしくみ」をうまく活用することも大切です。見守りの仕組みを取り入れることで、子どもがひとりで行動する時間のリスクを減らせるだけでなく、保護者の安心にもつながります。
ここでは、地域に根ざした取り組みや、公的サービスを防犯対策に取り入れる方法をご紹介します。
♢「子ども110番の家」やコンビニを活用しよう!
地域によっては、不審者に遭遇したときに駆け込める「子ども110番の家」が設置されているのをご存知でしょうか?
ステッカーが貼られた民家やお店が対象で、子どもが助けを求められる避難場所として機能しています。
また、夜でも明るく人の出入りが多いコンビニも、いざというときの避難先として心強い存在です。
帰り道に「ここなら助けを求められるね」と、子どもと一緒に確認しておくと安心です。
♢学校・塾と地域が連携する安全対策を確認しよう!
学校や塾では、地域の見守り活動と連携して、子どもの安全を支える取り組みが進んでいます。
- 集団下校の仕組み
- 地域ボランティアによるパトロール
- 保護者同士の送迎当番制
このような取り組みを導入しているところも多くあります。
保護者がこうした制度や取り組みに積極的に参加することで、地域全体の防犯意識を高めることができます。
お住まいの地域や学校によってどのような安全対策が行われているのか、ぜひ一度確認してみてくださいね。
♢自治体や警察の防犯メール・情報サービスを活用しよう!
多くの自治体や警察署では、不審者情報や防犯に関する注意喚起を配信する「防犯メールサービス」を提供しています。
- 「今日この地域で不審者情報があった」といった速報
- 子どもへの注意点や防犯啓発の情報
こういった情報をタイムリーに受け取ることができ、日常の防犯意識を高めるのに役立ちます。
登録は無料のことが多く、スマホから簡単に始められるので、ぜひチェックしておきたいサービスですね。
まとめ|子どもの安全は家庭・地域・社会で守る!
子どもの防犯対策は、家庭だけで考えるのではなく、地域や社会の力も借りながら、みんなで支えていくことが大切です。
親子でできる習慣づくりに加えて、地域の見守りや公的サービスをうまく取り入れることで、安心できる環境がぐっと広がりますよ。
今回ご紹介した防犯対策は、どれも今日から始められる、シンプルで実践的な工夫ばかりです。無理なく続けられる形で、少しずつ取り入れてみてくださいね。
子どもが安心して「ただいま」と帰ってこられるように。家庭・地域・社会、それぞれの力を合わせて、見守っていきましょう。
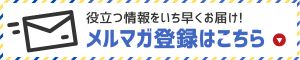
(執筆者:yuffy)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d27752b.c6966420.4d27752c.0b3d67c9/?me_id=1299852&item_id=10002410&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstarfocus%2Fcabinet%2F03921514%2Fsecuritybuzzer%2Fbuzzer_slide-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2777e2.d387b078.4d2777e3.e4661632/?me_id=1405250&item_id=10000035&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmixiofficial%2Fcabinet%2F11359285%2Fmt05w.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d2779b5.05e11fb7.4d2779b6.cf20b557/?me_id=1399192&item_id=10251908&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcaselandshop%2Fcabinet%2Ftop%2Fmja1513.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d277c37.f715f2d7.4d277c38.852634db/?me_id=1421741&item_id=10001131&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaibilife%2Fcabinet%2F10698021%2Fkidwatch.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)