最近よく耳にする「多様性」という言葉。
令和を生きる子どもたちにとって、多様性を認め合うことは必要なスキルです。
私は、小学校教諭、そして図書館司書教諭として10年以上、学校でたくさんの子どもたちと接してきました。
現代の学校には本当にいろいろな子がいます。
障がいをもつ子、外国籍の子、不登校の子—。
自分とちがう立場の相手に寄り添うのは、実はとても難しいことです。
差別や偏見を口に出してしまう子どもも、中にはいました。
また、頭では「仲良くしたい」と思っていても、いざ行動に移そうとすると戸惑う子、どう声をかけていいか分からない子もいます。
そんな時、そっと背中を押してくれるのが「絵本」です。
やさしい言葉と絵が、子どもたちに「ちがいっておもしろい」「ひとりひとり、みんな大切な存在なんだ」と気づかせてくれます。
今回は、多様性を受け入れる心を育てる絵本を5冊ご紹介します。
親子で一緒に、“ちがい”を楽しむ時間を作ってみませんか?
『わたしはあかねこ』 サトシン作
『わたしはあかねこ』(作:サトシン、絵:西村敏雄)は、「自分らしさ」や「自分の価値」を子どもに伝えたいときにぴったりの絵本です。
あらすじ
白ねこのお母さんと黒ねこのお父さんから生まれた5匹の子ねこ。
その中で、ひとりだけ赤い毛をもつ「あかねこ」は、自分の色を誇りに思っています。
しかし家族やきょうだいには理解されず、様々な手を使ってあかねこの毛の色を白や黒に近づけようとします。
ありのままの自分を認めてもらえない寂しさから、あかねこは家を飛び出します。
そして旅の途中で赤い毛をほめてくれる青ねこと出会い、自分らしさを大切にできる新しい居場所を見つけ、新しい虹色の家族を築くのです。
司書教諭としてのエピソード
この絵本は、よく読み聞かせで読んでいました。
最後にあかねこがあおねこと出会い、虹色の家族を作るところは「わぁ…!」と歓声が上がったのを覚えています。
子どもたちは「自分とちがう存在」にとても敏感です。
ときには、悪気のない一言で相手を傷つけてしまうこともあります。
そして思春期になると、「自分は周りから外れていないか」と不安を感じる子も増えます。
この絵本は、そんな子どもたちに
「他と違う存在を認めることの大切さ」
「自分だけの個性を誇りに思う気持ち」
を、やさしく伝えてくれます。
『さっちゃんのまほうのて』 たばたせいいち著
『さっちゃんのまほうのて』(たばたせいいち)は、幼稚園児の女の子「さっちゃん」が、障がいと向き合う心の成長を描いた絵本です。
あらすじ
さっちゃんは生まれつき右手に指がありません。
幼稚園のおままごと遊びで「お母さん役」をやりたかったさっちゃんですが、友達に「指のないお母さんは変だよ」と言われ、深く傷つき、幼稚園を飛び出します。
家に帰り「どうして自分の手はみんなと違うの?」と母にたずねると、
お母さんは「おなかのなかでけがをしてしまったの」と答えます。
さっちゃんは、「こんな手、いやだ」と泣きじゃくり、お母さんも一緒に涙します。
しばらく幼稚園を休むことになったさっちゃんですが、その間に家族や友達の心、そしてさっちゃん本人の心にも大きな変化があり、自分の手を受け入れていくのです。
司書教諭としてのエピソード
子どもというのは時に残酷で、目に入ったことや思ったことをそのまま口にしてしまうことがあります。親としては、そんな時こそ差別や偏見を持たず、自然に受け入れる気持ちを育ててほしいですよね。この絵本は、そんな心を育てる大きな助けになります。
小学校で読み聞かせをしたとき、子どもたちはしーんとして真剣に聞いていました。
読み終わると、目に涙をためる子もいたのを覚えています。
「ちがい」を持つ子どもの気持ちと葛藤、家族の支え、
そして自分を肯定する力が、まっすぐに描かれている作品です。
さっちゃん自身のキャラクターも明るくパワフルで、読後に元気をもらえます。
親目線でも涙なしには読めない一冊。
子どもだけでなく、大人にもぜひ読んでほしい絵本です。
『フレデリック』 レオ・レオニ作
『フレデリック』(作:レオ・レオニ、訳:谷川俊太郎)は、“ちょっと変わったねずみ”フレデリックが主人公の、心の豊かさや多様な生き方を描く絵本です。
あらすじ
牧場の古い石垣に住む野ねずみたち。
寒い冬に備えて、食糧や住まいの材料を集めて働いています。
そんな中、フレデリックだけは石の上でじっとしています。
「なぜ働かないの?」とねずみたちが尋ねると、「寒くて暗い冬の日のために、お日さまの光や色や言葉を集めているんだ」と答えます。
冬を迎え、冬眠の時期。ほら穴の中で食べ物も底を尽き、ねずみたちはふるえています。
その時、フレデリックが集めていた「ひかり・色・ことば」を仲間に語ると、みんなの心は温かくなり、元気を取り戻すのです。
司書教諭としてのエピソード
レオ・レオニといえば、小学2年生の国語教科書にも載っている『スイミー』を思い出す方も多いのではないでしょうか。
『スイミー』も、自分の個性を生かして成長する物語として愛されていて、私も大好きな絵本です。
でも、ここではあえて『フレデリック』を紹介したいのです。
学級には、フレデリックのような子が必ずいます。
みんなが認める「優等生」ではないけれど、静かに素敵な個性をもった子。
私は国語の授業で『スイミー』を学習したあとに、この本を読み聞かせしていました。
「みんなちがうけど、みんな必要なんだよ」と伝えたくて。
『フレデリック』は、
「生きていくために必要なのは食べ物や住まいだけじゃない。心を豊かにするものも大切だ」
という視点を、子どもたちにそっと教えてくれるやさしい絵本です。
『しげちゃん』 室井滋 作、長谷川義史 絵
『しげちゃん』(作:室井滋、絵:長谷川義史)は、男の子みたいな名前「しげる」を持つ女の子・しげちゃんが主人公の、自分の名前やアイデンティティに向き合う心温まる物語です。
あらすじ
俳優・室井滋さんの実体験から作られた絵本です。
1年生になったしげちゃんは、うきうきして小学校の入学式へ。
ところが、自分の机に行くと、男の子用の水色の紙で「しげる」と書かれたものが貼られていてショックを受けます。
女の子なのに男の子みたいな名前だと、友達や先生に間違われるたびに悲しくなり、自分の名前が嫌いになってしまいます。
名前を変えようと試行錯誤しますがうまくいかず、お母さんに相談すると、
「しげる」という名前に込められた意味や願いを教えてもらいます。
しげちゃんは少しずつ自分の名前を好きになっていきます。
司書教諭としてのエピソード
この絵本は、オリジナル教材として道徳の授業で取り扱ったことがあります。
参観日に合わせて実施し、授業の最後には保護者の方にお手紙でお子さんの名前の由来を書いていただきました。
子どもたちが嬉しそうに保護者からの想いを受け取っている姿がとても印象的でした。
「しげる」という名前には、体が弱く小さいうちに亡くなった兄の存在があり、
健康で強い子になってほしいという願いから、滋養の「滋」をつけたという由来があったそうです。
そんなエピソードを知った子どもたちは、自分や友達の名前の意味にも関心を持ち始めました。
友達の名前をからかうのは、子どもたちの世界ではよくあること。
でも、「名前を大事にする」ということは、その人を大事にするということです。
この絵本は、その大切さを自然に伝えてくれます。
『あおいめくろいめちゃいろのめ』 かこさとし
『あおいめくろいめちゃいろのめ』(作・絵:かこさとし)は、目の色が違う三人の子どもたちが主人公の、遊びと多様性がテーマの絵本です。
あらすじ
青い目、黒い目、茶色の目の三人は、みんな仲良しです。外で元気に遊びますが、どんな遊びをしても必ず誰かが泣いてしまい、なかなかみんなが楽しく遊べる方法が見つかりません。
三人は、どうすればみんなが楽しめるかアイデアを出し合い、試行錯誤していきます。
ところがある日、遊んでいる途中にハチに刺され、みんなの目がまっかっかに! 最後はみんなで泣いてしまいましたが、それでも一緒に遊び続ける三人の姿が描かれます。
司書教諭としてのエピソード
ちょっとインパクトのある絵柄が目を引く絵本です。
現代の小学校の学級には、外国籍の子が必ずといっていいほど在籍しています。
令和に入ってからは、毎年担任したどのクラスにも外国籍の子がいました。
言葉がうまく通じなかったり、宗教上の理由で学習や給食に配慮が必要だったり…
担任としては正直大変なこともありましたが、子どもたちは意外なほど自然に受け入れ、一緒に遊び始めるものです。
この絵本に登場する、目の色も考え方も違う3人は、そんな子どもたちの姿と重なります。
押しつけがましくなく、「ちがいを認めるってこういうことだよ」と教えてくれる一冊です。
まとめ|多様性を受け入れる素地を作るために
子どもたちは、時に残酷な言葉を口にしたり、「自分はみんなと同じだろうか」と不安になったりします。
そんなとき、絵本はやさしく寄り添い、「ちがいっていいね」「自分のままでいいんだよ」と背中を押してくれます。
今回ご紹介した5冊は、
見た目や名前、考え方、障がい、国籍や文化といったさまざまな“ちがい”をテーマに、多様性を受け入れる心を育ててくれる絵本です。
親子で一緒に読み、感想を話し合うことで、「友達がこうだったらどうする?」「あなたならどんな声をかける?」と
会話のきっかけが生まれます。
子どもが相手を思いやる心を育てる、貴重な時間になるはずです。
ぜひ、今日紹介した絵本から1冊選んで、親子で“ちがい”を楽しむ時間をつくってみてください。
暮らしのヒントがもっと見つかる「Craft Life」

部屋づくりのヒント、子どもとの暮らしをもっと楽しむアイデア、
そして、慌ただしい日々の中でも“ほっとひと息”つける時間の作り方——。
そんな“小さな工夫”が、毎日の家事や育児を驚くほどラクにしてくれます。
「Craft Life」では、子育て中のママ・パパに寄り添いながら、
家族みんなが心地よく暮らせるアイデアを日々発信しています。
たとえば…
- 片づけが自然と続く“しくみ”のつくり方
- 子どもの「やりたい!」を引き出す収納の工夫
- 家事をラクにする習慣の整え方 などなど。
読みやすく、すぐに実践できるヒントが満載です。
登録無料!暮らしの“ミニ知恵袋”が届きます
Craft Lifeのメルマガでは、忙しい毎日を助ける暮らしの工夫をギュッと凝縮してお届け。
すきま時間にサッと読めて、明日から役立つ情報ばかりです。
- 買ってよかった育児グッズ
- 忙しい日のための時短アイデア
- 赤ちゃんが生まれたらもらえるお金の話
登録はもちろん無料。
あなたの暮らしがもっとラクで、もっと楽しくなるヒントを受け取ってみませんか?
▼メルマガ登録はこちらから▼
(執筆者:AKKA)

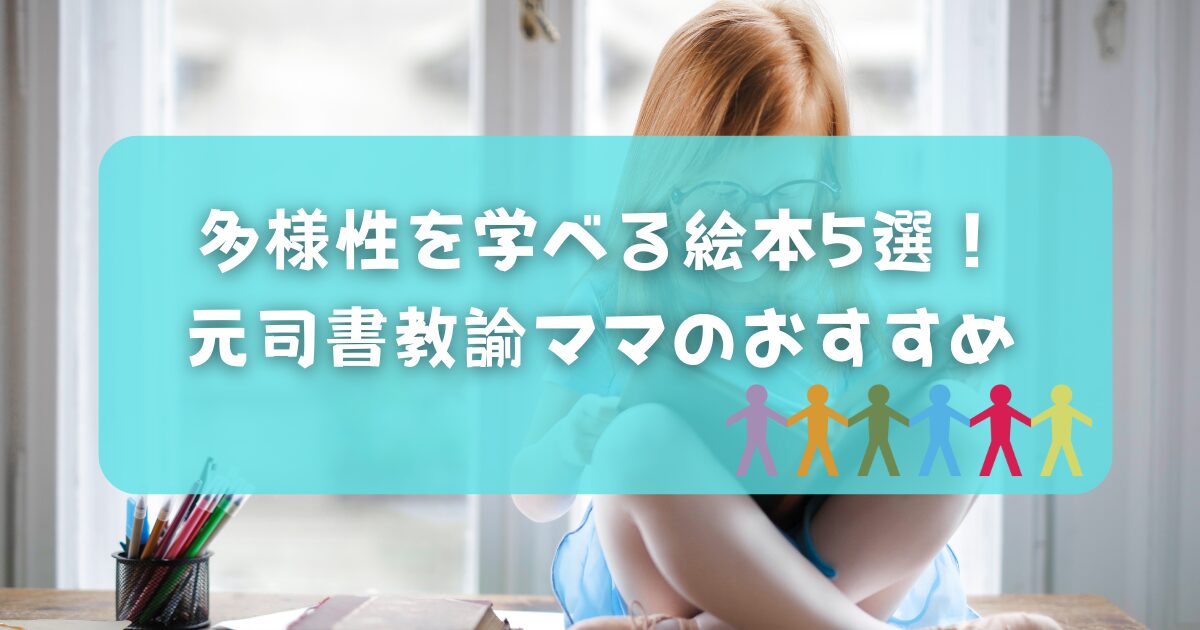
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48886168.7db985bd.48886169.a57495ce/?me_id=1285657&item_id=10397160&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00179%2Fbk489423730x.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=10137728&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4106%2F9784033304106.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=10185921&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0028%2F9784769020028_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=14674495&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1565%2F9784323071565.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4414811e.6c9303e0.4414811f.22f8515a/?me_id=1213310&item_id=10083088&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0102%2F9784032060102.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

